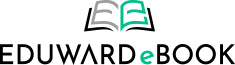寄稿者:大阪大学
《ニュース概要》
■研究成果のポイント
・ヒトiPS細胞から、生体肝と同様のZonation(機能的な多層構造)をもつ肝臓オルガノイド(mZ-HLO)を世界で初めて作製し、肝不全モデル動物での治療効果を実証
・Gulo遺伝子導入による高濃度アスコルビン酸(細胞内)とビリルビン暴露(細胞外)による各ゾーン特異的前駆細胞誘導と、両者の融合に基づく自己組織化によりZonation構築に成功
・肝疾患のメカニズム解明、創薬、個別化医療、再生医療への応用に期待
■概要
大阪大学大学院医学系研究科 武部貴則教授(器官システム創生学/ヒューマン・メタバース疾患研究拠点副拠点長)らの研究グループは、世界で初めて、ヒト多能性幹細胞(iPS細胞)から、生体肝臓に存在するZonation(機能的な多層構造)を備えた肝臓オルガノイドの創出に成功しました。遺伝子改変技術を組み合わせて、高濃度アスコルビン酸(細胞内)とビリルビン(細胞外)暴露を不均一に導入することにより、異なる肝細胞を誘導・自己組織化させることで、肝臓内のゾーン1〜3に相当する多層型構造を再現しました(図1)。さらに、得られたモデルから、ゾーンごとの特異的な遺伝子発現を制御するエピジェネティックなメカニズムを解明しました。
このオルガノイドを重度の肝不全モデル動物に移植したところ、血中アンモニアやビリルビンの濃度が大きく改善し、生存率も有意に向上しました。本技術は、肝疾患研究や薬物評価、再生医療の新たな基盤技術となることが期待されます。
本研究成果は、英国科学誌「Nature」に、4月17日(木)0時(日本時間)に公開されました。
■研究の背景
肝臓は、私たちの体内で栄養や薬の代謝、老廃物の処理を司る「代謝の司令塔」です。肝臓は、門脈から中心静脈に向かって、図2に示すように細胞が存在する位置に応じて異なる働きを担う Zonation(機能的な層構造)と呼ばれる空間特異性を持っています。Zonationが形成されることで、それぞれの領域で時として相反するような機能が発揮され、各々が複雑かつ補完的に代謝を担っています。肝臓の Zonation は、肝機能の多様性を支える基盤であり、疾患に応じてそれぞれのゾーンごとに、障害が進展していくことが知られていますが、末期肝不全などの状態では、すべてのゾーン機能が低下しており、深刻な状況に直結します。
近年、ヒト iPS 細胞から肝臓の立体組織(オルガノイド)構築を目指す研究が進んでいますが、各 Zonation に対応した肝細胞の分化誘導法は全く定まっていません。今後、肝臓を対象とした再生医療や創薬研究を飛躍的に加速するためには、ヒト肝臓の Zonation を再現した新たなオルガノイドモデルの開発が未踏課題となっていました。
■研究の内容
抗酸化物質であるアスコルビン酸は、ゾーン1に特異的な複数の遺伝子の発現を調節することで知られています。例えば糖新生、コレステロール合成、脂肪酸酸化などの機能は、ペリポータル(門脈周囲)肝細胞でアスコルビン酸によって促進されます。一方、ビリルビンはヘムの代謝産物であり、ペリセントラル(中心静脈)領域の代謝活性を高める働きがあり、ゾーン3に多く存在するCYP酵素の発現を促進したり、Wntシグナルを活性化することで間接的に影響を与えます。これらの知見から、アスコルビン酸とビリルビンがゾーン特異的な機能を制御する可能性が示唆されていました。
武部教授らの研究チームは、アスコルビン酸とビリルビンという2つの分子が、それぞれ Zonation に対応した肝細胞の分化を誘導することに着目し、遺伝子改変技術を用いることで同一シャーレ内で2つの異なった条件を導入することを試みました。Gulo遺伝子導入による高濃度アスコルビン酸(細胞内)とビリルビン暴露(細胞外)により作製された各ゾーン特異的前駆細胞を融合させる培養条件を見出し、世界で初めて、自己組織化により多層構造を持つ肝オルガノイド「mZ-HLO(multi-zonal human liver organoid)」を創出することに成功しました。
人間では、L-グロノラクトンオキシダーゼ(GULO)の偽遺伝子化によりアスコルビン酸合成能が失われています。そこで、げっ歯類の機能するGulo遺伝子の配列を参考に、薬剤誘導性にGuloの発現を制御可能なヒト iPS 細胞を作製し、オルガノイド誘導をおこなったところ、ペリポータル肝細胞(Z1-HLO)の特性を誘導できることを見出しました。一方で、Guloを導入していないヒト iPS 細胞から誘導したオルガノイドをビリルビンに暴露することで、ペリセントラル肝細胞(Z3-HLO)への分化が促されることを示しました。さらに、これらZ1-HLOとZ3-HLOの双方を同一シャーレ上で培養することで融合が促され、mZ-HLOが自律的に形成されることを発見しました。
これまで、人間においてはZonation形成を保証する分子機構は十分に理解されていません。そこで、本研究ではmZ-HLOモデルを活用することで、こうした Zonation の形成と維持が、弾力的なエピジェネティックな制御により分子レベルで精緻に制御されていることを明らかにしました。具体的には、ヒストン修飾酵素EP300が、ゾーン1誘導では酸化DNA修復酵素TET1と(図4 左)、ゾーン3誘導では低酸素応答因子HIF1Aと結合し(図4 右)、それぞれの Zonation に特有な遺伝子発現を制御していることを発見しました。これにより、各ゾーンの肝細胞が本来の機能を発揮し続けるための「遺伝子スイッチ」が、分子レベルで存在することがヒトの細胞を用いて初めて証明されました。
このmZ-HLOでは、遺伝子発現・代謝機能・薬物応答などにおいて、実際のヒト肝臓と類似した Zonation 特異的機能が観察されました。さらにこのオルガノイドを重度の肝不全モデル動物に移植したところ、単一のZonation特性しか存在しないオルガノイドを移植する群と比較して、血中アンモニアやビリルビンの濃度が大きく改善し、生存率も有意に向上しました。
■本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)
本研究は、ヒト肝臓の Zonation を in vitro(試験管内)で再現できる世界初の技術を確立したもので、肝疾患の研究、薬物代謝や毒性評価、さらには個別化医療の開発に向けた大きな前進となります。また、バイオ人工肝臓などをはじめとして次世代の肝機能再生のための基盤的細胞操作技術としても大きな可能性を秘めています。
今後はさらに成熟した肝機能の再現や、オルガノイドの大量生産技術の確立を進めることで、創薬や再生医療応用への展開が一層加速することが期待されます。
■特記事項
本研究成果は、2025年4月17日(木)0時(日本時間)に英国科学誌「Nature」(オンライン)に掲載されました。
タイトル:“Multi-zonal Liver Organoids from Human Pluripotent Stem Cells”
著者名:Hasan Al Reza, Connie Santangelo, Kentaro Iwasawa, Abid Al Reza, Sachiko Sekiya, Kathryn Glaser, Alexander Bondoc, Jonathan Merola and Takanori Takebe
DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08850-1
なお、本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の再生・細胞医療・遺伝子治療プログラム「機能強化型肝臓オルガノイドを用いたUTOpiAシステムの開発」および、CREST(革新的先端研究開発支援事業)「ヒト肝オルガノイドモデルを用いた内分泌系の破綻と炎症・線維化機構の解明」の一環で行われました。
そのほか本研究は、 Cincinnati Children’s Research Foundation CURE grant, Falk Transformational Award Program、New York Stem Cell Foundation, NIH Director’s New Innovator Award (DP2 DK128799-01), R01DK135478, AMEDの橋渡し研究プログラム「橋渡し研究推進による未来医療創出」、再生医療実現拠点ネットワークプログラム「ヒト肝臓オルガノイドによる血液凝固異常症の革新治療概念の実証」「内胚葉オルガノイドの線維化誘導とメカノスクリーン体系の創生」、肝炎等克服実用化研究事業・感染症実用化研究事業「ゲノム付きNAFLDオルガノイドパネルを用いた革新創薬概念の実証」「ヒトiPS細胞誘導性肝オルガノイドを用いた革新的疾患モデルの開発および肝線維化と発がんを抑止する治療法の創成」、CREST「仮想人体モデルを基盤とした感染症創薬プラットホームの構築」、肝炎等克服実用化研究事業「革新的オルガノイド技術を用いた肝線維化・発がん機構の解明と肝星細胞活性化制御をめざした治療法の創成」「MASLD/MASH肝がんの治療開発を目指すリピド・ゲノミクス研究3.0」の研究の一環として行われました。また、NIH grant UG3/UH3 DK119982、Cincinnati Center for Autoimmune Liver Disease Fellowship Award、 PHS Grant P30 DK078392 (Integrative Morphology Core and Pluripotent Stem Cell and Organoid Core) of the Digestive Disease Research Core Center in Cincinnati、武田科学振興財団、三菱財団、キャノン財団、JSTムーンショット型研究開発事業(JPMJMS2022, JPMJMS2033)、JSPS科研費(JP18H02800, JP19K22416)、そして世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)事業(大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(PRIMe))の協力を得て行われました。
■この研究についてひとこと
本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)
本研究は、ヒト肝臓の Zonation を in vitro(試験管内)で再現できる世界初の技術を確立したもので、肝疾患の研究、薬物代謝や毒性評価、さらには個別化医療の開発に向けた大きな前進となります。また、バイオ人工肝臓などをはじめとして次世代の肝機能再生のための基盤的細胞操作技術としても大きな可能性を秘めています。
今後はさらに成熟した肝機能の再現や、オルガノイドの大量生産技術の確立を進めることで、創薬や再生医療応用への展開が一層加速することが期待されます。
特記事項
本研究成果は、2025年4月17日(木)0時(日本時間)に英国科学誌「Nature」(オンライン)に掲載されました。
タイトル:“Multi-zonal Liver Organoids from Human Pluripotent Stem Cells”
著者名:Hasan Al Reza, Connie Santangelo, Kentaro Iwasawa, Abid Al Reza, Sachiko Sekiya, Kathryn Glaser, Alexander Bondoc, Jonathan Merola and Takanori Takebe
DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08850-1
なお、本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の再生・細胞医療・遺伝子治療プログラム「機能強化型肝臓オルガノイドを用いたUTOpiAシステムの開発」および、CREST(革新的先端研究開発支援事業)「ヒト肝オルガノイドモデルを用いた内分泌系の破綻と炎症・線維化機構の解明」の一環で行われました。
そのほか本研究は、 Cincinnati Children’s Research Foundation CURE grant, Falk Transformational Award Program、New York Stem Cell Foundation, NIH Director’s New Innovator Award (DP2 DK128799-01), R01DK135478, AMEDの橋渡し研究プログラム「橋渡し研究推進による未来医療創出」、再生医療実現拠点ネットワークプログラム「ヒト肝臓オルガノイドによる血液凝固異常症の革新治療概念の実証」「内胚葉オルガノイドの線維化誘導とメカノスクリーン体系の創生」、肝炎等克服実用化研究事業・感染症実用化研究事業「ゲノム付きNAFLDオルガノイドパネルを用いた革新創薬概念の実証」「ヒトiPS細胞誘導性肝オルガノイドを用いた革新的疾患モデルの開発および肝線維化と発がんを抑止する治療法の創成」、CREST「仮想人体モデルを基盤とした感染症創薬プラットホームの構築」、肝炎等克服実用化研究事業「革新的オルガノイド技術を用いた肝線維化・発がん機構の解明と肝星細胞活性化制御をめざした治療法の創成」「MASLD/MASH肝がんの治療開発を目指すリピド・ゲノミクス研究3.0」の研究の一環として行われました。また、NIH grant UG3/UH3 DK119982、Cincinnati Center for Autoimmune Liver Disease Fellowship Award、 PHS Grant P30 DK078392 (Integrative Morphology Core and Pluripotent Stem Cell and Organoid Core) of the Digestive Disease Research Core Center in Cincinnati、武田科学振興財団、三菱財団、キャノン財団、JSTムーンショット型研究開発事業(JPMJMS2022, JPMJMS2033)、JSPS科研費(JP18H02800, JP19K22416)、そして世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)事業(大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(PRIMe))の協力を得て行われました。
この研究についてひとこと
武部 貴則 医学系研究科 教授
もともとは、ヒトでだけ機能が欠失しているアスコルビン酸合成酵素である遺伝子Guloに着目して、機能するGuloを「ヒト」のiPS細胞にいれたら何が起こるのだろう?と興味本意で始めたサイドプロジェクトでした。最後まで頑張ったバングラデシュ出身の秀才Hasanくんに脱帽です!
・オルガノイド
幹細胞の自己組織化能力を活用して創出される、臓器あるいは組織の特徴を有する立体組織のことです。
・Gulo
ヒトでは機能が失われている、アスコルビン酸の合成酵素です。本研究では、マウスのGulo遺伝子を導入することでヒトiPS細胞内でのアスコルビン酸の合成に成功しました。
・門脈
消化器官から肝臓に血液を運ぶ静脈のことで、肝門脈とも呼ばれます。胃、すい臓、脾臓から様々な栄養素が門脈を通って肝臓に運ばれます。
■詳細はこちら※参照元のサイトを開きます
https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2025/20250417_1
メイン画像:上段:mZ-HLOの自己組織化。アスコルビン酸・ビリルビン暴露後のZ1(赤色), Z3(緑色)-HLOが融合していく過程を示している(20日目、23日目、27日目)【下段左:】シングルセル解析による肝オルガノイドのUMAPプロット【下段右】 肝オルガノイドのZonationの擬時間軌跡
下図:ヒストン修飾酵素EP300によるZonationの形成と維持の仕組み