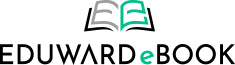寄稿者:関西医科大学
《ニュース概要》
【本件のポイント】
・小児鶏卵アレルギー患者の腸内細菌叢を解析
・酪酸産生菌※1である Faecalibacterium※2が豊富な患児は、将来の鶏卵アレルギーの寛解率が高いことを確認
・食物アレルギーの新たな治療戦略開発に期待
学校法人関西医科大学(大阪府枚方市 理事長・山下敏夫、学長・木梨達雄)医学部小児科学講座金子一成教授、赤川翔平講師らの研究チームは、鶏卵アレルギーを有する小児の腸内細菌叢を解析し、腸内細菌叢を構成する細菌のうち酪酸産生菌である Faecalibacterium(フィーカリバクテリウム)が多い患児では、将来の鶏卵アレルギーの寛解率が高いことを発見しました。
これは、鶏卵アレルギーを持つ小児患者 36 名の便を用いて遺伝子検査を行い、その後 2 年間以内に鶏卵アレルギーが寛解した小児(24 名)としなかった小児(12 名)の腸内細菌叢について、多様性と腸内細菌叢構成菌を比較した結果から分かったものです。
Faecalibacterium は腸内で酪酸を作り出し、その結果過剰な免疫を抑制する制御性 T 細胞※3を増やすことが知られていることから、早期寛解につながったものと考えられます。実際に、本研究において早期に鶏卵アレルギーが寛解した小児では血中の制御性 T 細胞が多いことが確認されました。
同研究チームは 2021 年に鶏卵アレルギーの患児の腸内細菌叢では健常小児と比較して酪酸産生菌が減少していることを報告しています。これらの研究成果は、腸内細菌叢を標的とした新たなアレルギーの予防・治療戦略につながる可能性が期待されます。
なお、本研究をまとめた論文が欧州科学誌『Allergy』(インパクトファクター:12.6)に 4 月 11 日(金)4 時(日本時間同 11 日 13 時)付で掲載されました。
■書誌情報
・掲載誌
「Allergy」(DOI:10.1111/all.16556)
・論文タイトル
Faecalibacterium in the Gut Microbiota Predicts Tolerance Acquisition in Pediatric Hen's Egg Allergy
・筆者
Akagawa S, Tsuji S, Nakai Y, Urakami C, Yamagishi M, Akagawa Y, Kaneko K
■本研究の背景
本邦における乳幼児の食物アレルギー有病率は 10%程度と高く、生命を脅かす重篤なアレルギー症状を来たすのみならず、患児や保護者の生活の質(quality of life: QOL)を大きく低下させるため、適切な治療が不可欠です。食物アレルギーの現在の基本的な治療指針は「正しい診断に基づいた必要最小限の原因食物除去」であり、この指針に沿った治療により鶏卵アレルギーでは 3 歳で 30%~70%、6 歳で 60~90%が耐性を獲得する(原因食物の摂取が可能となる)とされています。しかし、治療開始時点で耐性を獲得できるかどうか予測することは困難です。治療開始時点で耐性獲得の予測が可能となれば耐性獲得の可能性が低い患児に対して治療を加えることで、耐性獲得率の上昇につながる可能性があると考えられます。
一方で、ヒトの腸管内では 1,000 種類以上、38 兆個以上の細菌が腸内細菌叢を形成しており、宿主であるヒトの健康に大きく関与します。研究チームは 2021 年に鶏卵アレルギーを有する小児患者の腸内細菌叢では酪酸産生菌の減少に特徴づけられる腸内細菌叢の乱れ(dysbiosis)が存在することを報告しました。酪酸産生菌の代謝産物である酪酸は免疫抑制機能を持つ制御性 T 細胞(regulatory T cell: Treg)の分化誘導を促進するため、腸内細菌叢中の酪酸産生菌の多寡は食物アレルギー患者の臨床経過に影響を及ぼす可能性が考えられます。そこで、本研究では「鶏卵アレルギーの患児において、治療開始時点の腸内細菌叢に占める酪酸産生菌の多寡によって鶏卵アレルギー患者の耐性獲得を予測できるか否かを明らかにすること」を目的としました。
■本研究の概要
研究チームは、鶏卵アレルギーを持つ小児患者 36 名(男児 24 名、年齢中央値 2.9 歳[四分位範囲 1.8-4.1])の便を用いて遺伝子検査を行い、その後 2 年間以内に鶏卵アレルギーが寛解した小児(寛解群:24 名)(男児 16 例、年齢中央値 2.8 歳[四分位範囲 1.7-3.9])としなかった小児(非寛解群:12 名(男児 8 例、年齢中央値 3.2 歳[四分位範囲 2.0-4.9]))の腸内細菌叢について、多様性と腸内細菌叢構成菌を比較しました。その上で、有意差を認めた菌属については ROC(receiver operating characteristic curve)曲線を用いて、耐性獲得を最も正確に予測するカットオフ値を算出しました。また治療前に採血した 23例の末梢血の CD4+細胞に占める Treg 比率について 2 群で比較しました。
■本研究の成果
まず、寛解群・非寛解群の両群において、年齢・性別による差はありませんでした。2 群の腸内細菌叢は Bray–Curtis 非類似度による主座標分析における permutational analysis of variance(PERMANOVA)解析で統計学的に異なっていることが分かりました(p=0.034)。腸内細菌叢の多様性については 2 群間で有意な差はありませんでした。
属レベルでの解析では、寛解群では Bacteroides( 31.1% )、Faecalibacterium(13.5%)、Blautia(6.4%)が多く存在していました。一方で、非寛解群では Bacteroides(25.3%)、Bifidobacterium(19.2%)、Blautia(9.1%)が多く存在していました。占有率上位 10 菌属について2 群間で比較したところ、寛解群において有意に Faecalibacterium(13.5% vs. 2.7%, p<0.001)が多いことが分かりました。また、ROC曲線下面積は 0.86(p<0.001)であり、最適なカットオフ値は 7.1%で、2 年後の耐性獲得を予測する感度は 83%、特異度は 83%と良好であり、腸内細菌叢に占める Faecalibacterium によって、将来の寛解を高い精度で予測できることを明らかにしました。また、末梢血 Treg 比率は寛解群は非寛解群と比較して有意に高いことが分かりました(4.7% vs. 1.6%, p=0.011)。
■今後の可能性
本研究は鶏卵アレルギーの患児において、治療開始時点の腸内細菌叢に占める酪酸産生菌(Faecalibacterium)の多寡によって鶏卵アレルギー患者の耐性獲得を予測できる可能性を世界で初めて示したものです。酪酸はナイーブ T 細胞を Treg に分化させ、過剰な免疫応答を抑制するため酪酸産生菌の減少がアレルギー疾患の発症や重症化・難治化に関与している可能性があり、酪酸産生菌の減少に特徴づけられる腸内細菌叢の乱れ(dysbiosis)の是正はアレルギー疾患の新たな治療標的となる可能性があります。具体的には、プレバイオティクスやプロバイオティクス※4などを用いて腸内細菌叢をより良い状態に改善させることが、食物アレルギーの新しい予防法・治療法の開発につながるものと期待されます。
■用語解説
※1 酪酸産生菌c
ヒトの腸内において、食物繊維を発酵・分解することで酪酸を産生することができる菌の総称です。酪酸は、腸管内で制御性 T 細胞の分化誘導を促進し、過剰な免疫反応を抑える働きがあることが知られています。
※2 Faecalibacterium
Bacillota 門 Clostridia 綱 Eubacteriales 目 Oscillospiraceae 科に属するグラム陰性嫌気性桿菌。ヒトを含むさまざまな生物の消化管内に多数存在し、個人差はあるもののヒトの全腸内細菌のおよそ 5%程度を占めると考えられています。酪酸を作り出し、腸の健康や免疫調整に関与するとされ、次世代のプロバイオティクスとして期待されています。
※3 制御性 T 細胞
リンパ球のうちのひとつ、T 細胞の一種で、過剰な免疫応答を抑制する役割を担っています。近年、アレルギー疾患や自己免疫疾患との関連が報告されており、注目を集めています。
※4 プレバイオティクス/プロバイオティクス
プレバイオティクスとは、大腸内の特定の細菌の増殖および活性を選択的に変化させることでヒトに有利な影響を及ぼし、健康を改善する難消化性食品成分です。具体的には、オリゴ糖や食物繊維などがあげられます。一方、プロバイオティクスとは、腸内細菌叢のバランスを改善することで宿主の健康に好影響を及ぼす生きた微生物や、微生物を含む食品を指します。具体的には、ビフィズス菌や乳酸菌製剤、ヨーグルト、乳酸菌飲料などがあります。
詳細はこちら※参照元のサイトを開きます
https://www.kmu.ac.jp/news/laaes7000000vpnj-att/20250411Press_Release.pdf