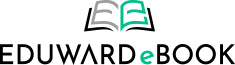寄稿者:大阪公立大学
《ニュース概要》
■概要
近年、猫や犬に対する高度医療の発展を背景に、イヌ iPS 細胞を活用した新たな治療法の開発や、遺伝性疾患をはじめとする病態の解明への期待が高まっています。iPS 細胞の培養には、細胞が培養皿の底面で接着および増殖するための足場となる培養基質が必要です。現在、イヌ iPS 細胞の培養基質には、主にヒト由来の組換えタンパク質が使用されています。しかし、イヌにとっては異種成分であり、免疫拒絶や安全性の懸念から、臨床応用には適していないという課題があります。
大阪公立大学大学院獣医学研究科の志々田 康平大学院生(博士課程 3 年)、生田 悠衣氏(当時:大阪府立大学生命環境科学域 6 年)、鳩谷 晋吾教授らの研究グループは、イヌ由来の遺伝子を大腸菌に導入し、培養基質となるビトロネクチン(VTN)と、その N 末端を一部欠損させた変異体(VTN-N)を作製しました。そして、これらのイヌ由来VTN および VTN-N を用い、イヌの iPS 細胞の接着性や増殖性について従来使用されているヒト由来 VTN と比較検証しました。その結果、イヌ由来の VTN および VTN-N は、ヒト由来 VTN と同等の性能を示し、iPS 細胞の未分化能および多分化能も維持されることが確認されました。
本研究成果は、2025 年 9 月 16 日に国際学術誌「Regenerative Therapy」に、オンライン掲載されました。
志々田 康平大学院生
鳩谷 晋吾教授
私たちは幹細胞研究を将来の臨床応用へつなげることを目指し、日々研究に取り組んでいます。本研究がイヌ iPS 細胞の実用化への一助となり、獣医再生医療の発展に少しでも貢献できれば幸いです。
図. イヌ由来のビトロネクチンの作製
■研究の背景
iPS 細胞は、皮膚や血液などの体細胞に特定の遺伝子を導入することで作製される特殊な細胞で、あらゆる細胞へ分化できる能力を持っています。近年ではイヌにおいても iPS 細胞の樹立、培養が可能となり、その特性を生かして、移植治療、病態解析、新薬開発などへの応用が期待されています。iPS 細胞の培養には「培養基質」と呼ばれる足場が必要で、現在は主にヒト由来の組換えタンパク質が利用されています。しかし、これらはイヌにとって異種由来の成分であり、免疫拒絶反応や安全性のリスクが懸念されるため、臨床応用には不向きです。これまでイヌ由来の培養基質に関する報告はなく、安全で実用的なイヌ iPS 細胞の応用を実現するためには、種特異的な培養基質の開発が不可欠であると考えられます。
■研究の内容
本研究では、イヌ由来の遺伝子を大腸菌に導入し、培養基質となるビトロネクチン(VTN)と、その N 末端を一部欠損させた変異体(VTN-N)を人工的に作製しました。これらを培養皿にコーティングし、イヌ iPS 細胞の接着・増殖能を評価しました。さらに、iPS 細胞の特性である未分化能と多分化能について、ヒト由来 VTN と比較検討しました。その結果、イヌiPS 細胞はイヌ由来 VTN および VTN-N 上で、ヒト由来基質と同等の接着率・増殖率を示しました。また、未分化能と多分化能の維持も確認され、とくに未分化能の指標である OCT3/4や SOX2 の発現が上昇していることが明らかとなりました。
■期待される効果・今後の展開
今回の成果は、イヌ iPS 細胞を異種由来成分を使用せず安定的に培養できる道を開いた点で大きな意義があります。これにより、イヌで多くみられる心臓病や神経疾患、血液疾患などの難治性疾患に対する再生医療の臨床応用が現実に近づくと期待されます。加えて、イヌビトロネクチンは大腸菌で安定的かつ低コストで生産できるため、研究用途から臨床応用まで幅広く利用できる基盤技術となり得ます。
■資金情報
本研究は、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2139)、JSPS 科研費(22H02525)、および公益財団法人 G-7 奨学財団の支援を受けて実施しました。
■掲載誌情報
【発表雑誌】
Regenerative Therapy
【論文名】
Recombinant production of canine vitronectin for optimizing the culture ofcanine induced pluripotent stem cells
【著者】
Kohei Shishida, Yui Ikuta, Hiroko Sugisaki, Kazuto Kimura, Jun Katahira,Masaya Tsukamoto, Shingo Hatoya
【掲載 URL】
https://doi.org/10.1016/j.reth.2025.09.002