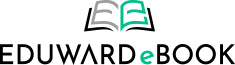寄稿者:東北大学 / 科学技術振興機構
《ニュース概要》
【発表のポイント】
・肝臓でブドウ糖を産生する糖新生(注 1)では、運動の強さごとに、ブドウ糖を作る材料(基質(注 2))を使い分けることで、運動中のエネルギー供給が維持されていることをマウスを用いた実験で明らかにしました。
・肝臓の酸化還元反応(注 3)を促進させ糖新生の効率を上げると、運動の強さに関わらず持久力が上昇することが分かりました。
・この仕組みは、運動能の向上法や肥満を改善し、サルコペニア(注 4)を予防する手法につながることが期待されます。
【概要】
体の中には、空腹時や運動時にブドウ糖を作り出して低血糖を防ぐ糖新生と呼ばれる仕組みが備わっています。糖新生では、脂肪分解によりできるグリセロールや、筋肉で作られる乳酸などの材料(基質)をもとに、主に肝臓でブドウ糖が産生されます。
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝・内分泌内科学分野および東北大学病院糖尿病代謝・内分泌内科の金子慶三講師、堀内嵩弘特任研究員、片桐秀樹教授らのグループは、運動の強さに応じて、肝臓での糖新生に使われる基質が異なることを明らかにしました。ゆっくり走る軽い運動ではグリセロール、速く走る激しい運動では乳酸を基質とした肝臓の糖新生が活発化することにより、運動が持続できていることを発見しました。さらに、肝臓の酸化還元反応を促進させると、糖新生が亢進(こうしん)し、運動持久力が向上することも確認されました。
本研究は運動能の向上法につながるとともに、肥満・サルコペニアへの対策の新たなアプローチにつながるものと期待されます。
本研究成果は、2025年9月18日(日本時間9月18日)に英国学術誌NatureMetabolism 誌に掲載されました。
【詳細な説明】
研究の背景と経緯
ブドウ糖は、私たちが活動するために欠かせないエネルギー源です。血糖値とは血中のブドウ糖濃度のことです。食事中の炭水化物を分解してブドウ糖に変えることができますが、体の中には、お腹が空いた時や運動中などに備えて、ブドウ糖を作り出すことで低血糖を防ぎ、全身にエネルギーを届ける仕組みが備わっています。この仕組みは糖新生と呼ばれ、主に肝臓で行われます。糖新生では、脂肪や筋肉からのさまざまな材料(基質)を用い、肝臓でいくつかの代謝反応を経てブドウ糖が合成されます。運動中の筋肉は血液中のブドウ糖をエネルギー源として大量に消費するため、それに応じるべく、肝臓では糖新生が促進されます。運動中の糖新生の代表的な基質は、筋肉の活動によって生じる乳酸と考えられ、それを用いてブドウ糖を作る仕組みを中心に研究が進められてきました。一方で、肝臓内の糖新生には、脂肪分解によりできるグリセロールを基質にする仕組みも存在しますが、これらの糖新生の仕組みの役割の違いは解明されていませんでし。
東北大学の片桐秀樹教授らの研究グループは、これまでに肝臓における糖や脂質の代謝が全身の代謝バランスを維持する仕組みについて長年研究を行ってきました(Science 312: 1656-1659, 2006, Science 322:1250-1254, 2008, CellMetabolism 16: 825-832, 2012, Cell Reports 30: 112415, 2023 など)。今回、肝臓が「運動中はどの基質をどのように用いてブドウ糖を作り、エネルギー源を供給しているか」を明らかにするための研究を行いました。
■研究の内容
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝・内分泌内科学分野および東北大学病院糖尿病代謝・内分泌内科の金子慶三(かねこ けいぞう)講師、堀内嵩弘(ほりうち たかひろ)特任研究員、片桐秀樹(かたぎり ひでき)教授らのグループは、遺伝子改変技術(注 5)を用いて、乳酸もしくはグリセロールからの糖新生ができないマウスを作製し、それぞれのマウスに長時間ゆっくり走る場合と短時間で速く走る場合の二種類の運動をさせて、代謝に関する解析を行いました。その結果、乳酸からの糖新生ができないマウスでは、対照の通常マウスに比べて速く走る運動の走行時間が減少したのに対し、グリセロールからの糖新生ができないマウスは、対照の通常マウスに比べてゆっくり走る運動の走行時間が減少しました。このことから、激しい運動では乳酸、軽い運動ではグリセロールと、運動の強さに合わせて、基質を使い分けてブドウ糖を作ることで、効率よく運動中のエネルギー供給を維持していることを明らかにしました。
一方で、乳酸から糖新生ができないマウスをゆっくり走らせたところ、グリセロールからの糖新生が亢進し、走行時間が増加しました。グリセロールから糖新生ができないマウスでは、乳酸からの糖新生が亢進して、速く走る運動の走行時間が増加しました(上図)。この糖新生が亢進し運動能が上昇した原因を調べる過程で、さまざまな代謝反応を調節する酸化還元反応に着目しました。体の中では、NAD⁺(酸化型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)がNADH(還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)になり、また NADHが NAD⁺に戻る、という酸化還元のサイクルが繰り返されることで、代謝の流れが促進されます。そこで NAD⁺を増やして NADH にする反応を促進させるタンパク質をマウスの肝臓に作らせたところ、ゆっくり走る場合はグリセロールを、速く走る場合は乳酸を使った糖新生を活用して、トレーニング効果よりも顕著に、どちらの強度の運動においても持続時間も延ばすことができることが分かりました(下図)。
これらの結果から、運動時の肝臓の糖新生では、長時間ゆっくり走る場合は豊富に存在する脂肪分解によりできるグリセロールを、短時間に速く走る場合には筋肉で素早く作られる乳酸を用いて、ブドウ糖を産生し運動を持続させることが分かりました。さらに、肝臓の酸化還元バランスを調節すると、運動中に肝臓に流れ込んだグリセロールや乳酸をさらに効率よくグルコースに変えることが可能となり、強弱いずれの運動に対しても、持続時間を増やすことができることが分かりました。
■今後の展開
本研究では、肝臓が、ブドウ糖としてエネルギーを筋肉に供給することにより運動能を決めていること、さらには、基質の種類ごとに異なる糖新生代謝経路がある意義を明らかにしました。今回、マウスで得られた結果はヒトにも応用できる可能性があり、これまで考えられていなかった「肝臓にフォーカスを当てた運動能力を向上させる手法」の開発につながるものと考えられます。さらに、乳酸は筋肉から、グリセロールは脂肪から作られることから、このメカニズムを制御することで、筋量を維持し脂肪を燃やすこと、つまり、サルコペニアを予防し効率よく減量できる運動療法や新たな肥満治療法を生み出すことにもつながると期待されます。
■画像解説
上図:ゆっくり走る軽い運動ではグリセロールを、速く走る激しい運動では乳酸を用いた糖新生で作られたグルコースが運動中のエネルギー源となる。
A. 乳酸から糖新生ができないマウスでは速く走る運動の走行時間が減少し、ゆっくり走る運動の走行時間が増加した。
B. グリセロールから糖新生ができないマウスはゆっくり走る運動の走行時間が減少し、速く走る運動の走行時間が増加した。
下図: 肝臓の酸化還元反応の促進は運動中のグリセロールや乳酸からの糖新生を増やし、運動能を向上させる。
A.B. 乳酸やグリセロールからの糖新生ができないマウスは、肝臓の酸化還元バランスが NAD⁺が増える方向に変化していた。
C. 肝臓の酸化還元反応を促進させると、対照の通常マウスではゆっくり走る運動の走行時間が上昇した。一方、グリセロールから糖新生ができないマウスでは、走行時間は増加しなかった。
D. 肝臓の酸化還元反応を促進させると、対照の通常マウスでは速く走る運動の走行時間が上昇した。一方、乳酸から糖新生ができないマウスでは、走行時間は増加しなかった。
【謝辞】
本研究は、文部科学省科学研究費補助金(課題番号:20H05694, 22K08642)、科学技術振興機構(JST) ムーンショット型研究開発事業「目標 2:2050 年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」の研究課題「恒常性の理解と制御による糖尿病および併発疾患の克服(プロジェクトマネージャー:片桐 秀樹、課題番号:JPMJMS2023)の支援を受けて実施されました。
ムーンショット型研究開発事業 片桐秀樹プロジェクトマネージャーからのコメント:肝臓での糖新生が運動能力を決めていること、さらに、運動強度ごとに基質やそれを作り出す組織(筋や脂肪)と連携していることが明らかとなりました。本成果は、運動能力を向上させ、筋量を保って減量する運動法の提唱や新たな手法の開発につながるものとして、本ムーンショット目標にまさに合致するものと考えます。
【用語説明】
注1. 糖新生:
ブドウ糖は、私たちの体にとって欠かせないエネルギー源で、食事に含まれる炭水化物から補われます。血糖値とは、血液中のブドウ糖の濃度を指します。食事がとれない時や、ブドウ糖を多く消費する運動中には、体は主に肝臓でブドウ糖を新たに作り出し、血糖値を保つ仕組みを持っています。この仕組みを「糖新生」と呼びます。
注2. 基質:
生物の体の中では、たくさんの物質がさまざまな化学反応を起こし、別の物質に変わることを繰り返しています。こうした生命活動の仕組みを「代謝」と呼びます。また、ひとつひとつの化学反応を「代謝反応」、これらの反応に関わる物質を「代謝物」と呼びます。代謝を行うことで、生物はエネルギーを使ったり、生み出したりしています。糖新生は新しくブドウ糖を作る代謝のひとつであり、ブドウ糖を作る材料となる代謝物のことを「基質」と呼びます。
注3. 酸化還元反応:
酸化還元反応は電子のやりとりを含む代謝反応の 1 つです。反応が進む時に電子を渡すことを「酸化」、電子を受け取ることを「還元」と呼びます。この酸化還元反応はさまざまな代謝反応を調節しています。特に、NAD⁺(酸化型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)とNADH(還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)の反応はとても重要です。体の中では電子の受け渡しを介して、NAD⁺が NADH になり、今度は NADH が NAD⁺に戻るという酸化還元のサイクルが繰り返されています。多くの代謝反応が NAD⁺と NADH の反応を介して促進されます。糖新生における代謝においても、この酸化還元反応が存在しています。
注4. サルコペニア:
サルコペニアとは、加齢により筋肉量や筋力が低下する状態のことです。高齢化が進む日本では、このサルコペニアを抱える高齢者が増えており、転倒や骨折、要介護のリスクを高めることから、重要な社会的課題となっています。
注5. 遺伝子改変技術:
遺伝子改変技術とは、体に必要なタンパク質を作るための設計図となる遺伝子を、人の手で操作する技術です。この技術を使うことで、特定のタンパク質が作られないようにすることもできます。今回の研究では、この技術を用いて、グリセロールや乳酸からの糖新生に必須のタンパク質が作れないマウスを作製しました。
【論文情報】
タイトル:Redox-dependent liver gluconeogenesis impacts different intensity exercise in mice
酸化還元反応に依存する肝糖新生は運動強度にかかわらず運動能を制御する
著者:Takahiro Horiuchi, Keizo Kaneko*, Shinichiro Hosaka, Kenji Uno, Seitaro Tomiyama, Kei Takahashi, Maya Yamato, Akira Endo, Hiroto Sugawara, Yohei Kawana, Yoichiro Asai, Shinjiro Kodama, Junta Imai, Seiya Mizuno, Satoru Takahashi, Atsushi Takasaki, Hiraku Ono, Koutaro Yokote, Rae Maeda, Yuki Sugiura, and Hideki Katagiri*
堀内 嵩弘、金子 慶三*、穂坂 真一郎、宇野 健司、冨山 晴太郎、高橋 圭、大和真弥、遠藤 章、菅原 裕人、川名 洋平、浅井 洋一郎、児玉 慎二郎、今井 淳太、水野 聖哉、高橋 智、髙崎 敦史、小野 啓、横手 幸太郎、前田 黎、杉浦 悠毅、片桐 秀樹*
*責任著者:
東北大学病院 糖尿病代謝・内分泌内科講師 金子 慶三(かねこ けいぞう)
東北大学大学院医学系研究科 糖尿病代謝・内分泌内科学分野教授 片桐 秀樹(かたぎり ひでき)
掲載誌:Nature Metabolism
DOI:10.1038/s42255-025-01373-z
URL:https://www.nature.com/articles/s42255-025-01373-z