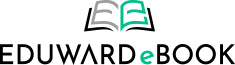寄稿者: 岡山大学 / 東京大学 / 慶應義塾大学 / 国際医療福祉大学
《ニュース概要》
■発表のポイント
・心不全モデルマウスを用いた解析により、心不全の状態で活性化される線維芽細胞※1)が cMYC※2)を介して CXCL1※3)を分泌し、心筋細胞※4)の機能を低下させる新たなメカニズムを発見しました。
・従来は構造支持細胞と考えられていた線維芽細胞が、心不全の進行に直接関与しうることを世界で初めて示し、非心筋細胞による病態制御の重要性を明らかにしました。
・心不全は高齢化社会で患者数が増加する重大疾患で、本研究は、心筋以外の細胞を標的とした新しい治療法の開発につながる可能性があり、臨床応用が期待されます。
岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)循環器内科学の湯浅慎介教授、東京大学大学院医学系研究科先端循環器医科学講座の小室仁日本学術振興会特別研究員、慶應義塾大学医学部内科学教室(循環器)の家田真樹教授および国際医療福祉大学の小室一成教授らは、心不全の進行に“心臓の線維芽細胞”が深く関与する新たな仕組みを明らかにしました。
研究チームは、心不全モデルマウスを用いた解析により、これまで「構造を支持しているだけの細胞」と考えられていた線維芽細胞が、c-MYC というタンパク質を介して CXCL1 という分子を分泌し、心筋細胞の CXCR2※5)という受容体を介して心不全を増悪させることを発見しました。さらに、この c-MYC-CXCL1-CXCR2 経路の働きをブロックすることで心不全の悪化を防げることも示され、心不全の新たな原因解明とともに、非心筋細胞を標的とする新しい治療法の可能性が示唆されました。本研究成果は基礎研究段階ですが、ヒト心不全患者でも同様のメカニズムが確認されており、今後の臨床応用が期待されます。
本成果は、2025 年 9 月 10 日、国際学術誌「Nature Cardiovascular Research」に掲載されました。
「重症心不全はいまだに治療法が限られています。これまでは心不全の原因は心筋細胞であると考えられてきましたが、今回の研究から心筋細胞だけでなく線維芽細胞も心不全の原因となり得ることが示されました。新たな治療法の開発に向けた研究に取り組んでいきたいと考えています。」(湯浅教授)
■現状
心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、息切れやむくみなどの症状が進行する深刻な疾患であり、国内だけでも 100 万人以上が罹患していると推定されています。その死亡率は依然として高く、社会的・経済的な影響も大きいことから、新たな治療法の開発が強く求められています。これまでの心不全研究や現在の治療薬は、心臓を動かす主役である心筋細胞に焦点を当てたものが中心でした。しかし、心臓を構成する細胞の約 70%以上は心筋細胞以外の非心筋細胞であり、そのうち約 15%を占める線維芽細胞は、主に心臓の構造を支える役割があると考えられてきました。近年、これら非心筋細胞にも大事な役割があることが注目され始めていますが、その詳細はまだ明らかになっていませんでした。
■研究成果の内容
本研究では、心不全モデルマウスを用いて、心不全時に活性化される特定の線維芽細胞の集団を特定しました。この細胞集団は、がん研究でよく知られているc-MYCという細胞の働きを調節するタンパク質が顕著に発現しており、これが CXCL1 という細胞間の情報伝達に関わる物質を誘導していることが分かりました。さらに、CXCL1は心筋細胞に存在する受け皿CXCR2 に作用し、心筋細胞の収縮機能を直接低下させていることを明らかにしました。具体的には、cMYCを線維芽細胞で欠失させたマウスでは、心不全モデルでの心機能の悪化が抑えられ、逆に c-MYCを強制的に発現させたマウスでは心機能が著しく低下しました。また、CXCL1–CXCR2 の作用を妨げる薬剤を投与することで、心不全による心機能の低下を効果的に抑えられることも示されました。これらの知見は、心不全の発症・進行において、心筋細胞だけでなく、線維芽細胞も積極的に関与していることを示す重要な証拠となります。
加えて、ヒトの心不全患者由来の心臓組織を解析したところ、マウスで得られた知見と同様に、心不全の線維芽細胞において c-MYC が発現し、c-MYC–CXCL1 のシグナルが活性化されることが示唆されており、本研究の成果がヒト心不全にも応用可能であることが確認されました(下図)。
■社会的な意義
今回の成果は、これまで“裏方”と考えられていた線維芽細胞が、心不全の進行に重要な役割を果たしている可能性を示した点で画期的です。従来の治療法の多くが心筋細胞を標的としていたのに対し、非心筋細胞を新たな標的とする治療戦略の確立に向けた大きな一歩となります。
今後は、CXCL1–CXCR2 経路を標的とした新しい治療薬の開発や、ヒト心不全患者を対象とした臨床研究への応用が期待されます。心不全は高齢化とともに患者数が増加しており、より多様で効果的な治療法の実現が求められています。本研究のように、従来注目されてこなかった細胞に光を当てることで、難治性疾患の新たな理解と治療の糸口が得られると考えられます。
■論文情報
論文名:Heart failure-specific cardiac fibroblasts contribute to cardiac dysfunction via c-MYC-CXCL1–CXCR2 axis
掲載紙:Nature Cardiovascular Research
著者:Jin Komuro, Hisayuki Hashimoto, Toshiomi Katsuki, Dai Kusumoto, Manami Katoh, Toshiyuki Ko, Masamichi Ito, Mikako Katagiri, Masayuki Kubota, Shintaro Yamada, Takahiro Nakamura,Yohei Akiba, Thukaa Kouka, Kaoruko Komuro, Mai Kimura, Shogo Ito, Seitaro Nomura, Issei Komuro, Keiichi Fukuda, Shinsuke Yuasa*, Masaki Ieda.
DOI:10.1038/s44161-025-00698-y
URL:https://www.nature.com/articles/s44161-025-00698-y
■研究資金
本研究は、 JSPS 科研費 JP16H05304, JP16K15415, JP18K08047, JP19H03622, JP20H03678,JP20K08461, JP20K08193, JP24K02452, JP21J12663, JP23KJ0353, JP23K23798, JP23K18581,JP22H00471, JP25H01050, JP21H05045, JP24K23940、公益財団法人 先進医薬研究振興財団、公益財団法人 大和証券ヘルス財団、日本循環器学会基礎研究助成(2020)、公益財団法人 日本心臓財団研究助成、日本心不全学会 (ノバルティスファーマ)基礎研究助成、公益財団法人 榊原記念財団研究助成、公益財団法人 日本応用酵素協会、公益財団法人 循環器病研究振興財団、公益財団法人 持田記念医学薬学振興財団、公益財団法人 MSD 生命科学財団、公益財団法人 武田科学振興財団、公益財団法人 中外創薬科学財団、公益財団法人 三菱財団、公益財団法人アステラス病態代謝研究会、UTEC-UTokyo FSI 研究助成プログラム、科学技術振興機構(JST)FOREST プログラム(JPMJFR210U)、慶應義塾大学医学部研究奨励費、潮田記念基金 慶應義塾博士課程学生研究支援プログラム、日本医療研究開発機構(AMED)ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(ゲノム医療実現推進プラットフォーム・先端ゲノム研究開発)「マルチオミックス連関による循環器疾患における次世代型精密医療の実現」(代表:小室一成)、難治性疾患実用化研究事業「オールジャパン拡張型心筋症ゲノムコホート研究によるゲノム医療の発展」(代表:野村征太郎)、生命科学・創薬研究支援基盤事業「先端的1細胞オミックス・エピトランスクリプトーム解析の支援と高度化」(代表:油谷浩幸)、循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「エピゲノム編集とシングルセル解析を統合したシーズ探索による心不全の新規治療法開発」(代表:小室一成)、循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「心臓分泌性因子による心不全発症機序の解明と治療法開発」(代表:小室一成)、再生医療実現拠点ネットワークプログラム「心筋細胞を標的とした遺伝子治療・変異修復治療による心臓疾患治療法の開発」(代表:野村征太郎)、ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム・次世代医療基盤を支えるゲノム・オミックス解析「循環器疾患におけるシングルセルマルチオミックス層別化の実現」(代表:小室一成)、革新的先端研究開発支援事業「ヒト心不全における心筋 DNA 損傷の病的意義の解明とその制御」(代表:小室一成)、ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業「大規模疾患コホート・アカデミア連携を基盤とするオミックス解析・サーベイランス体制の整備による新興感染症重症化リスク因子の探索」(代表:山梨裕司)、難治性疾患実用化研究事業「難病のゲノム医療実現に向けた全ゲノム解析の実施基盤の構築と実践」(代表:國土典宏)、ゲノム研究を創薬等出口に繋げる研究開発プログラム「デジタロミクスによる心不全ストレス応答の機序解明と精密医療」(代表:野村征太郎)、「心不全シングルセルゲノミクス創薬」(代表:小室一成)、先端国際共同研究推進プログラム(医療分野国際科学技術共同研究開発推進)「クロマチン分子病理学による精密医療の実現」(代表:白髭克彦)、難治性疾患実用化研究事業「日本循環器研究コンソーシアムによる難治性心血管疾患のエビデンス創出」(代表:小室一成)、循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「心臓リハビリ模倣治療法の多面的な開発」(代表:野村征太郎)等の支援によって行われました。
■補足・用語説明
※1)線維芽細胞:心臓や皮膚などの組織に存在し、細胞外構造をつくる働きを持つ細胞。
※2)c-MYC:細胞の成長や分裂を調整するタンパク質。がん細胞などで高く発現することが知られている。
※3)CXCL1:細胞間の情報伝達に使われる物質の一種で、炎症反応などにも関与する。
※4)心筋細胞:心臓の収縮を担う筋肉の細胞。
※5)CXCR2:CXCL1 などのシグナルを受け取る受容体(受け皿)として機能するタンパク質。
■画像解説
メイン画像:心臓内にはさまざまな細胞があり、大多数を占めていると考えられていた心筋細胞は 20−30%程度、線維芽細胞は 15−30%程度で、繊維芽細胞にもいろいろなタイプの細胞がいる。心不全に特異的な線維芽細胞が c-MYC-CXCL1-CXCR2 経路を介して、心筋細胞に直接障害を与え、心不全を引き起こすことが示された。
下図 :ヒトサンプル研究成果のまとめ
ヒトの心臓サンプルとヒト iPS 細胞を用いた研究にてマウス同様に心臓線維芽細胞と心筋細胞のc-MYC-CXCL1-CXCR2 経路が心不全に関与する可能性が示唆された。