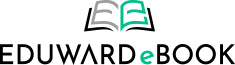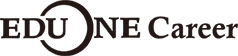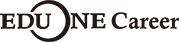寄稿者: 岐阜大学
《ニュース概要》
【本研究のポイント】
・狂犬病は重篤な神経症状と高い致死率を特徴とする人獣共通感染症で、その治療法は未だ確立されていません。
・狂犬病ウイルスの L タンパク質は P タンパク質と結合することで RNA 合成酵素として機能するため、これらタンパク質の結合を阻害することは狂犬病治療薬開発の戦略のひとつとして有望視されています。
・これまでに、L タンパク質の C 末端領域が P タンパク質との結合に関与することはわかっていましたが、その領域の P タンパク質との結合面ではない部位がどのような役割をもつのかは不明でした。
・本研究では、C 末端領域の P タンパク質との結合面ではない部分が L タンパク質の P タンパク質結合能、RNA 合成酵素機能、ならびに安定性に重要となることを明らかにしました。
・本成果は、狂犬病治療薬開発に向けた基盤情報となることが期待されます。
【研究概要】
岐阜大学応用生物科学部共同獣医学科の伊藤直人教授らの研究グループは、北海道大学大学ワクチン研究開発拠点の澤洋文教授、同大学人獣共通感染症国際共同研究所の佐々木道仁准教授、および五十嵐学准教授との共同研究で、狂犬病ウイルス L タンパク質 1)のC 末端領域の新たな役割を明らかにしました。
狂犬病ウイルス 2) の L タンパク質は、P タンパク質 3)と結合することで RNA 合成酵素として機能し、ウイルス増殖の中心的な役割を担います(図 1)。したがって、L タンパク質と Pタンパク質の結合(L-P 結合)を阻害することは、未だ存在しない狂犬病治療薬開発において極めて有望な戦略となります。L タンパク質の C 末端領域は、P タンパク質との結合面を形成することが報告されています。一方で、結合面を形成しない部位がどのような役割をもつかは不明でした。本研究では、C 末端領域の P タンパク質との結合面ではない部位がL タンパク質の P タンパク質結合能、RNA 合成酵素機能、および安定性のそれぞれに重要となることを明らかにしました。この成果は、狂犬病治療薬開発における基盤情報となることが期待されます。
本研究成果は、日本時間 2025 年 3 月 11 日 23:00 に米国微生物学会誌『Journalof Virology』のオンライン版で発表されます。
図中のN、P、M、G、およびLが書かれた四角形は、ウイルスゲノム上にコードされた5つのウイルスタンパク質(それぞれN、P、M、G、およびLタンパク質)の遺伝子を示します。ウイルスゲノムはNタンパク質により包まれており、さらにそこへL-P複合体が結合します。
【研究背景】
狂犬病は、重篤な神経症状と高い致死性を特徴とするウイルス性の人獣共通感染症です。本病に対する有効なワクチンが存在する一方で、確立された治療法はなく、ワクチンの普及が十分でないアジアおよびアフリカの発展途上国を中心に年間推計 5.9 万人が犠牲となっています。そのため、治療法の確立は、狂犬病の犠牲者を減少させるための喫緊の課題です。
その病原体である狂犬病ウイルスは、自身のゲノム RNA の複製や mRNA の転写を行うための RNA 合成酵素として L タンパク質をもちます。L タンパク質が機能するためには、ウイルスの P タンパク質と結合し L-P 複合体を形成することが不可欠です。そのため、LP 結合を阻害することは、狂犬病治療薬開発の戦略として極めて有力です。最近、L-P 複合体の立体構造が決定されたことで、L タンパク質の C 末端領域が P タンパク質との結合面を形成することが明らかになりました。しかし、C 末端領域内の結合面を形成しない部位がどのような役割をもつのかは不明でした。
【研究成果】
本研究では、以前に伊藤教授らのグループにより P タンパク質結合能と RNA 合成酵素機能の両方に重要となることが明らかにされた L タンパク質の NPYNE 配列 4)に注目しました。L-P 複合体の立体構造における NPYNE 配列の位置を確認したところ、この配列は C 末端領域の P タンパク質との結合面から遠く離れた部分に位置していることがわかりました(図 2)。このことから、C 末端領域の P タンパク質との結合面でない部分も機能的に重要となることが明らかになりました。
図2 L-P複合体の立体構造におけるC末端領域およびNPYNE配列の位置
本図は、Horwitzらによって解かれた狂犬病ウイルスのL-P複合体構造に基づいて作図されました(Horwitz et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2020; タンパク質構造データバンクID:6UEB)。Lタンパク質をリボンモデルで表しました。また、Pタンパク質およびLタンパク質上のPタンパク質との結合面を形成するアミノ酸残基を分子表面表示しました。NPYNE配列は、Pタンパク質との結合面から離れた部位に位置していることがわかります。
NPYNE 配列が位置する部位の機能的役割を詳しく解明するために、NPYNE 配列に様々な変異をもつ狂犬病ウイルスや L タンパク質の変異体を作出し、それらの性状解析を行いました。その結果、1929 位のアスパラギン残基(NPYNE 配列の 1 つ目の N)が P タンパク質結合能と RNA 合成酵素機能の両方に重要となることがわかりました。また、1932 位のアスパラギン残基(2 つ目の N)および 1933 位のグルタミン酸残基(E)がそれぞれ RNA 合成酵素機能および P タンパク質結合能に重要となることも明らかになりました。さらに、NPYNE 配列が L タンパク質の安定性に重要となることが示されました。
以上の結果より、C 末端領域の NPYNE 配列が位置する部分が L タンパク質の P タンパク質結合能、RNA 合成酵素機能、および安定性のそれぞれに重要となることが明らかになりました。
【研究の意義】
一般に、2 つのタンパク質分子の結合には分子間の結合面に位置する領域が重要になることから、L タンパク質 C 末端領域の P タンパク質との結合面となる部位が L-P 結合に重要な役割を担っていると考えられています。しかしその一方で、本研究の成績は P タンパク質との結合面でない部位も L-P 結合に関与していることを明確に示しています。これは、P タンパク質との結合面以外の部位が L-P 結合阻害薬開発の標的となる可能性を示す初めての知見です。
さらに、本研究では NPYNE 配列の位置する C 末端領域が P タンパク質との結合だけでなく、L タンパク質の RNA 合成酵素機能や安定性にも重要となることを明らかにしました。このことから、L タンパク質 C 末端領域を標的とし、L-P 結合を阻害する化合物が発見されれば、RNA 合成酵素機能および安定性の両者の低下がもたらす相乗効果により効率的にウイルス増殖を抑制する狂犬病治療薬となる可能性が期待されます。
以上の成果は、L-P 複合体の構造や機能についての新たな知見を提供し、狂犬病治療薬開発における有力な基盤情報となります。
【用語解説】
1)L タンパク質
狂犬病ウイルスを構成するタンパク質のひとつ。ウイルスゲノムの複製および mRNA の転写・成熟に必要なすべての酵素機能を備えた多機能性タンパク質である。RNA 合成酵素として、ウイルス増殖の中心的役割を担っている。
2)狂犬病ウイルス
モノネガウイルス目ラブドウイルス科リッサウイルス属に分類されるウイルス。非分節のマイナス鎖 RNA をゲノムとしてもつ。特徴的な弾丸状の粒子を形成する。すべての哺乳動物に感染し、致死的な脳炎を主徴とする狂犬病を引き起こす。
3)P タンパク質
狂犬病ウイルスを構成するタンパク質のひとつ。L タンパク質の必須共因子としてはたらくだけでなく、宿主自然免疫系の回避にも関与する。
4)NPYNE 配列(アスパラギン–プロリン–チロシン–アスパラギン–グルタミン酸配列)
狂犬病ウイルス L タンパク質の 1929 位から 1933 位に見出された 5 つのアミノ酸残基の並び(各アルファベットはアミノ酸の一文字表記に対応)。狂犬病ウイルス間で完全に保存されている。以前、伊藤教授らのグループにより L タンパク質の P タンパク質結合能とRNA 合成酵素機能に重要となることが報告された(Nakagawa et al., J. Virol.,2017)。
【論文情報】
雑誌名:Journal of Virology
論文タイトル:Functional dissection of the C-terminal domain of rabies virus RNA polymerase L protein
著者 : Fumiki Izumi, Machiko Makino, Michihito Sasaki, Kento Nakagawa, Tatsuki Takahashi, Shoko Nishiyama, Yuji Fujii, Misuzu Okajima, Tatsunori Masatani, Manabu Igarashi, Hirofumi Sawa, Makoto Sugiyama, Naoto Ito
DOI: 10.1128/jvi.02082-24
詳細はこちら(※参照元のサイトを開きます)
https://www.gifu-u.ac.jp/news/research/2025/03/entry12-14266.html