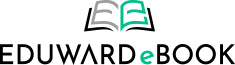寄稿者:筑波大学 / 千葉大学
《ニュース概要》
一つの受精卵から双子が生まれる仕組みについて、ウニの初期胚を用いて調べました。その結果、ウニの1個体を初期段階で半分に分けても、それぞれの断片が自ら体の設計図を描き直し、完全な個体へと発生する細胞の動きと遺伝子の働きを明らかにしました。
19世紀末、ドイツの発生学者ハンス・ドリーシュは、ウニの受精卵を2細胞期で分離すると、それぞれの細胞が独立して完全な個体に成長することを初めて示しました。しかしながら、分離後に胚がどのようにして胚軸(正常な体を形成するための体軸)を作り直し、正常な発生を遂げるのか、その詳細な発生過程や分子メカニズムは、100年以上にわたり解明されていませんでした。
本研究では、顕微鏡技術と分子生物学の手法を用いて、ウニの1個体を初期段階で半分に分けても、それぞれの断片が自ら体の設計図を描き直し、完全な個体へと発生する仕組みを解明しました。また、「自分で自分の体を組み立て直す力(自己組織化)」の背後にある細胞の動きと遺伝子の働きを捉え、個体の胚軸が再構築される過程を可視化することに成功しました。今回の発見は、「なぜ一つの受精卵から二人の命が生まれるのか?」という、生命科学における長年の謎に対して、ウニというモデル生物を通じて新たな視点を提供するものです。私たち人間の一卵性双生児のしくみを考える上でも、今後の発生研究における重要な手がかりになると考えられます。
■研究代表者
・筑波大学生命環境系
谷口 俊介 准教授
・千葉大学大学院医学研究院
露崎 弘毅 特任講師
■研究の背景
19 世紀末、ドイツの生物学者ハンス・ドリーシュ(Hans Driesch)は、2 細胞期(受精卵が最初の分裂を終えて 2 つの細胞になった段階)のウニ胚を分離すると、それぞれの細胞から完全なウニの幼生が形成されることを見いだしました。これは、胚が自分自身を調節して完全な個体を作る「調節発生注1)」と呼ばれる現象であり、生物の発生があらかじめ決められたものではなく、柔軟に自己組織化できることを示す歴史的発見でした。しかし、分離後に胚がどのようにして胚軸注2)を作り直し、正常な発生を遂げるのか、その詳細な発生過程や分子メカニズムは、100 年以上にわたり解明されていませんでした。
ウニは体外受精で発生が進むため観察や実験操作が容易で、胚が透明なことから生きたまま内部の細胞挙動を詳細に観察できます。またゲノムや発生に関わる遺伝子の情報も蓄積されており、発生メカニズムの解明に適したモデル生物です。実際、Driesch の実験以来、ウニは胚の自己組織化現象を研究する代表的なモデルとなってきました。本研究グループは、ウニ胚を用いて、胚を半分にしても 2 つの個体ができる仕組みを分子レベルで解明することを目指しました。
■研究内容と成果
まず、バフンウニ(Hemicentrotus pulcherrimus)について、2 細胞期のウニ胚を人工的に分離し、それぞれの細胞(半胚)がどのように発生を進めるかを詳細に観察しました。通常の胚では細胞分裂を経て中空の球状の胞胚になりますが、半胚では一度平板状(シート状)に広がり、その後に杯状、さらに球状へと形を変えて最終的に小さな胞胚となりました。興味深いことに、また、Driesch が報告したように、この胞胚は正常胚よりやや小さいものの、ほぼ通常と同様の発生過程を経て健全な幼生へと成長しました(図1)。
この特殊な形態変化を支えるメカニズムをライブイメージング注3)と分子生物学的手法を用いて調べたところ、タンパク質複合体アクトミオシン注4)の収縮と細胞間をつなぐセプテートジャンクション注5)が協調して働くことで、細胞シート全体が球状へと形を変えることが分かりました。
さらに、この過程において、シート状の細胞配置では一時的に前後軸(あたまとおしりを結ぶ体軸)が乱れるものの、その後、正常化し、続いて背腹軸(背と腹を結ぶ体軸)も正常に形成されることが確認されました(図3)。このとき、体のおしり側の位置情報を決定する Wnt/β カテニンシグナル注6)が再活性化されることで、あたま側の領域が移動し軸が修復されます。これにより、通常は背側を決定するシグナル分子 Nodal 注7)の働きを抑制する転写因子 FoxQ2 注8)の分布が適切に整い、最終的に背腹軸の形成も可能となりました。
以上の結果から、たとえ胚が初期段階で半分に分かれても、それぞれの断片が自律的に形を整え、体の軸を作り直して完全な個体へと育つ仕組みが明らかになりました。この発見は、成長過程に偶然半分に分かれてしまっても、しっかりとした個体がなぜか誕生するという長年の疑問に、発生生物学的な視点から新たな手がかりを与える重要な成果です。
■今後の展開
本研究により、ウニ胚をモデルとして胚の調節発生を支える分子基盤が解明されました。これは 100年以上前に示された現象に現代の科学で光を当てたものであり、同様の自己組織化現象が他の生物種でもどのように起こるのか、今後の研究への展望を開くものです。ウニで明らかになった軸再形成の仕組みや発生プログラムの柔軟性は、哺乳類を含む他の動物胚にも共通する普遍的な原理である可能性があり、ヒトにおける一卵性双生児の形成メカニズムについても、解明の手がかりになると考えられます。今後は、ウニ以外のモデル生物や培養細胞を用いて、この自己組織化能力が進化的にどのように保存されているか、またどの因子が双生児形成の誘導に関与し得るかを調べる予定です。こうした研究は、再生医療などにもつながると期待されます。
■参考図
メイン画像:本研究の概要
2細胞期のウニ胚をそれぞれの細胞に分離すると、双子ができる。その過程の詳細は不明であったが、一度シート状に育った細胞集団が丸くなって個体になることが分かった。
下図: ウニ胚の調節発生ではあたま側の領域が移動することで正常な前後軸を形成
半分胚では、シート状・杯状の段階において、正常胚と同様に将来のあたまとおしりは対極に存在する。それが、球状の構造になる際に一時的にあたまとおしりが隣り合う状態になるが、その後、あたま側の運命だけが細胞移動を伴わない状態でおしりの対極まで移動する。つまり、あたまを決める遺伝子(ここでは FoxQ2)の発現領域が次々に移動していき、最終的におしりの対極で発現する状態でストップし、正常な前後軸を形成する。
■用語解説
注1) 調節発生
初期胚の細胞が分割・移植などで配置を変えられても、胚全体として正常な発生運命を調節できる発生様式。ウニやカエル、哺乳類など進化的に後口動物に分類される生物で顕著に見られる。一方、昆虫や貝類などでは、初期胚の各部分に将来の運命があらかじめ決まっており、切り離すとその部位が欠損したまま発生が進むモザイク発生様式をとる。
注2) 胚軸
正常な体の形成に不可欠な概念線。多くの動物では身体の基本的な対称性を決める複数の軸がある。ウニやヒトの場合、頭-尾方向を決める前後軸(一次軸)と、背-腹方向を決める背腹軸(二次軸)の二軸が重要。ヒトではさらに左右軸も加わる。
注3) ライブイメージング
光学顕微鏡を用いて生きたままの生き物の動きや細胞の変化を直接観察する手法。今回はウニ胚の細胞膜と核を蛍光タンパク質によって標識し、それをレーザー光で光らせたものを観察した。
注4) アクトミオシン(アクチン-ミオシン)
細胞の骨格を構成するタンパク質「アクチン」と、その上を移動して筋収縮や細胞収縮を引き起こすモータータンパク質「ミオシン」の複合体。細胞の形を変えたり分裂したりするときに重要な役割を果たす。胚の形態形成では、細胞が収縮することで組織が湾曲したり折り畳まれたりする。
注5) セプテートジャンクション
主に無脊椎動物(節足動物や棘皮動物など)の細胞間に見られる接着構造の一種。隣接する細胞同士を帯状につなぎ、特に上皮細胞において組織の形を保つ役割を持つ。胚発生の過程でも組織の形態形成に関与する。
注6) Wnt/β カテニンシグナル
胚の発生や再生を制御する代表的な細胞内シグナル伝達経路の一つ。細胞外因子 Wnt が細胞膜上の受容体に結合すると、細胞内で β カテニンというタンパク質を安定化させ、遺伝子発現を変化させる。胚の体軸決定や細胞の増殖・分化制御など、多岐にわたる生物学的現象に関与する。
注7) Nodal(ノーダル)
発生過程で細胞から分泌されるシグナル分子(たんぱく質)で、TGF-β ファミリーに属する。Nodalはさまざまな生物で胚の背腹軸や左右軸を決定する誘導因子として働き、ウニ胚では腹側(将来口ができる側)の指定に必須。
注8) FoxQ2
動物の初期発生における転写因子(遺伝子のスイッチを入れる調節タンパク質)の一つ。ウニ胚では受精卵の動物極側(将来の前方・頭側領域)で発現し、胚の二次軸形成(背腹軸の確立)に影響を与えることが知られている。Nodal 経路を抑制する働きがある。
■研究資金
本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR194C, JPMJPR1945)研究成果展開事業 A-STEP(JPMJTR204E; 2019‒2024 年度)、日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)(23K23933; 2022‒2025 年度)、基盤研究(C)(23K11312; 2023‒2025 年度)、挑戦的研究(萌芽)(24K21959; 2024‒2027 年度)、若手研究(19K20406; 2019‒2022 年度)などの助成を受けて実施されました。
■掲載論文
【題名】
Unraveling the regulative development and molecular mechanisms of identical sea urchin twins
(ウニの双子胚における発生調節と分子機構の解明)
【著者名】
Haruka Suzuki, Junko Yaguchi, Koki Tsuyuzaki, *Shunsuke Yaguchi (*責任著者)
【掲載誌】
Nature Communications
【掲載日】
2025 年 9 月 5 日
【DOI】
10.1038/s41467-025-63111-z