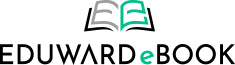寄稿者:宮崎大学
《ニュース概要》
国立大学法人宮崎大学(宮崎県宮崎市、学長:鮫島 浩、以下「宮崎大学」)、および宮崎市(市長:清山知憲)は、あぶらとりフィルムで採取した皮脂に含まれるRNAを利用してヒトの肌や体の状態を把握する非侵襲の解析方法が、ネコにおける感染症ウイルスの検出に応用可能であることを確認しました。
本研究成果は2025年9月3日(水)、宮崎市シーガイア・コンベンションセンターで開催された第168回日本獣医学会学術集会にて発表しました。
1. 背景
ネコには病気を引き起こす多くのウイルス感染症があり、宮崎県をはじめとして各地で感染者が出ている重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:SFTS)*3や、猫後天性免疫不全症候群(Feline Immunodeficiency Virus:FIV感染症、いわゆる猫エイズ)などは、近年大きな社会問題となっています。ネコの診療現場では、検査者として獣医師や愛玩動物看護師が直接対応することが多く、血液検査では注射針を使用します。こういった検査はネコの負担が大きいだけでなく、検査者にも感染リスクやけがの危険が伴うため、安全性の向上は極めて重要です。
現在、あぶらとりフィルムで採取したヒトの皮脂から感染症ウイルスのRNAを検出し、ウイルスと人体の反応を同時に調べる簡便で非侵襲な評価技術の研究が行われています*2。そこで研究チームは、ネコの皮脂から感染症ウイルスのRNAを検出することを試みました。あぶらとりフィルム一枚で非侵襲的かつ簡便に採取した皮脂を利用することでこれらのウイルスの検出が簡易に行えることは、獣医学的観点だけでなく、ヒト、動物の健康、環境への影響を一体的に考えるOne Healthの観点からも大きな意義があります。
*2 Non-invasive SARS-CoV-2 RNA detection and human transcriptome analysis using skin surface lipids. Sci Rep. 14, 26057 (2024)
*3 SFTSはマダニが媒介するSFTSウイルスによる人獣共通感染症で、発熱、消化器症状、白血球・血小板減少などを特徴とします。重症化すると多臓器不全や神経症状を引き起こすことがあり、ヒト、ネコいずれにおいても高い致死率を示します。近年は国内での報告例も増加しており、先日、三重県の獣医師がSFTSに感染して死亡したことが報告され、注意喚起が強まっています。
2. 研究手法・成果
本研究では、あぶらとりフィルムから抽出したネコの皮脂を用いて、SFTSウイルス、およびFIV(猫エイズウイルス)の検出に挑戦しました。偽陰性注1を防ぐために皮脂からハウスキーピング遺伝子注2の増幅を確認するステップを取り入れていますが、検査者が素手で検体を採取する可能性があるため、ヒトとネコのハウスキーピング遺伝子を見分ける必要性にも留意しました。
研究の結果、ネコ皮脂からのRNA検出感度が最も高く、ヒトやネコのDNA/RNAと識別可能なハウスキーピング遺伝子プライマーの開発に成功しました。また、ネコの複数の部位から検体を採取し、RNA検出感度や採取のしやすさを比較した結果、皮脂の採取に最適な部位は耳であると判断しました(写真A、B、C)。
さらに、あぶらとりフィルムから抽出したネコの皮脂から FIV および SFTS ウイルスの RNA の検出に成功しました。加えて、血清由来の検査結果と皮脂由来の評価結果において、Ct 値注 3 に大きな差がないことを確認しました。以上の結果から、この新しい検査法は従来法同等の信頼性を有することが示されました。
3. 波及効果・今後の予定
本研究では、ネコの皮脂から感染症ウイルスの RNA を検出することに成功しました。猫の全身状態を把握するためには、血液を用いた各種検査も重要です。併せて、本研究で見いだした手法を状況に応じて活用することで、ウイルス感染症に対してより非侵襲で安全性の高い評価法の開発が期待されます。これは、診療現場での負担軽減や感染リスク低減に貢献し、One Health の実現にもつながると考えられます。今後は、さらにこの検査法の最適化と普及を進め、幅広い現場での活用を目指します。
本研究は、宮崎大学農学部獣医学領域、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター、宮崎市の共同研究として実施し、宮崎市シーガイア・コンベンションセンターで開催された第168回日本獣医学会学術集会にて発表しました。
【用語解説】
注1 偽陰性:
実際には陽性であるにもかかわらず、検査結果が陰性と判定されてしまう誤検出のことです。サンプルの品質低下や検出感度の問題などが原因となり、病気や感染症の見逃しにつながるため、診断精度を保つ上で防止が重要です。
注2 ハウスキーピング遺伝子:
細胞の基本的な機能を維持するために常に発現している遺伝子の総称です。細胞内で安定して発現しているため、検体の品質管理や内部対照として利用され、正確な遺伝子検出や発現解析を行う際の基準となります。
注3 Ct値(Cycle threshold value):
リアルタイムPCR検査において、蛍光シグナルが検出限界を初めて超えるサイクル数を示す値です。Ct値が低いほど、検体中に含まれる標的遺伝子(ウイルスRNAなど)の量が多いことを意味し、逆にCt値が高いほど、遺伝子量が少ないことを示します。感染症診断においては、Ct値が重要な指標となり、検出感度やウイルス量の推定に活用されます。