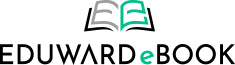寄稿者:北海道大学
《ニュース概要》
■ポイント
・獣医師や動物行動/福祉研究者が持つ動物福祉の考え方について社会科学的に日英で比較。
・日英ともに、動物の「5 つの自由」に優先順位がつけられていることを可視化。
・英国と比較し、日本では動物の「正常な行動を発現する自由」が重要視されない傾向。
■概要
北海道大学 One Health リサーチセンターの大谷祐紀特任助教(研究当時 同大学大学院獣医学研究院博士研究員、エジンバラ大学客員博士研究員)らの研究グループは、日英の獣医師及び動物行動/福祉学研究者を対象としたアンケート調査を行い、両国の動物福祉への考え方の差異や共通点を調べました。
動物福祉は英国から始まった概念で「動物の精神的・身体的状態」と定義されています。近年、多様性や持続可能性への意識の高まりから、動物福祉への配慮が国際的な関心事となっています。動物福祉には基本原則があり、動物は「飢え・渇きからの自由」「恐怖・抑圧からの自由」「不快からの自由」「痛み・怪我・疾病からの自由」「正常な行動を発現する自由」の「5 つの自由」が保障されることが重要です。一方で、動物福祉は「科学的、倫理的、経済的、文化的、社会的、宗教的、政治的な側面を持つ複雑で多面的な概念」とも定義され、様々な要因がその理解や解釈、社会実装に影響を与えます。研究グループは、日本土着の動物への考え方や価値観、社会通念、教育が、動物福祉に対する考え方に影響すると仮説を立て、日本と英国で獣医師や動物福祉の研究者を対象としたアンケート調査を行いました。
その結果、日本と英国の獣医師・動物福祉学研究者は、動物福祉に対して概ね同様の価値観を持っている一方、「正常な行動を発現する自由」への考えが異なり、その違いが両国で推奨されている動物の管理方法にも影響していることが分かりました。
私たちの生活は、たくさんの動物によって支えられています。動物福祉は、動物と人がより良い関係で暮らす社会の基礎となる考え方です。一方、日本で育まれてきた動物観や文化と、英国発祥である動物福祉の両立にはバランスの取れた熟議が必要です。本研究では、英国と日本の共通点・差異を社会科学的に可視化することで、議論の一助となる客観的データを提供しました。
なお、本研究成果は、2025 年 8 月 6 日(水)公開の Animal Welfare 誌にオンライン掲載されました。
【背景】
動物福祉(アニマルウェルフェアと同義)は英国から始まった概念で「動物の精神的・身体的状態」と定義されています(国際獣疫事務局:WOAH*1)。
近年、多様性や持続可能性への意識の高まりから、動物福祉の評価とその向上が国際的な関心事となっています。動物福祉には基本原則があり、人に管理される伴侶動物(ペット)や家畜動物、実験動物、動物園動物には「飢え・渇きからの自由」「恐怖・抑圧からの自由」「不快からの自由」「痛み・怪我・疾病からの自由」「正常な行動を発現する自由」の「5 つの自由」が保障されることが求められます。一方で、動物福祉は「科学的、倫理的、経済的、文化的、社会的、宗教的、政治的な側面を持つ複雑で多面的な概念」とも定義され(WOAH)、文化や社会通念、宗教、経済など様々な要因が動物福祉の理解や解釈、動物管理の手法に影響を与えます。同じ島国であり、経済発展や生活スタイルも近い日本と英国を比較した場合でも、たとえば日本では猫を完全に室内で飼育することが推奨される一方、英国では猫が外へのアクセスを持つことが理想と考えられるなど、“良(善)い”とされる動物管理には違いがあります。また、逃れられない苦痛を取り除くという観点から、動物の安楽死は獣医学的に重要な処置の一つですが、伴侶動物の安楽死に対する日英の態度の違いは顕著であり、1 動物病院あたりの安楽死症例数は、英国で日本の約 27 倍というデータも報告されています。
私たちの生活はたくさんの動物に支えられており、その動物たちに良い福祉を提供することは、私たちの責任です。しかし、日本でこれまで育まれ、大事にされてきた動物との関わり方や価値観と動物福祉の考え方はしばしば相容れず、その両立に向けた熟議が求められています。本研究では、動物福祉への配慮を実践し、教育・普及する立場である獣医師及び動物行動/福祉学研究者が有する動物福祉への考え方・態度について日英で比較し、両国の共通点や差異を調査しました。
【研究手法】
2021 年 11 月から 2022 年 1 月にかけ、日本と英国の獣医師及び動物行動/福祉学研究者を対象としたオンラインアンケートを実施しました。質問は動物の「5 つの自由」をベースとして独自に作成し、日本語と英語で同じ内容としました。得た回答について統計学的な解析を行い、両国が持つ特徴を比較しました。
【研究成果】
日本から 321 名、英国から 212 名の有効回答を用い、解析を実施しました。結果、日英ともに、「5つの自由」のうち「飢え・渇きからの自由」「恐怖・抑圧からの自由」「痛み・怪我・疾病からの自由」が、伴侶動物にとって最も重要と考えている獣医師・動物行動/福祉学研究者が多いことが分かりました。これら生存に直結する自由と比較し、「不快からの自由」「正常な行動を発現する自由」は両国に共通して重要と認識されづらい一方、特に日本では英国よりも「正常な行動を発現する自由」を最も重要と考える回答者割合が少ない結果が示されました(下図:英国が 68%に対し、日本は 42%)。
次に、猫の飼養への考え方を調べるため、日英で共通したシナリオを設定し、猫の福祉に関して質問しました。その結果、日英ともにシナリオ中の猫は室内を主として飼養することを推奨する回答者がほとんどでした。しかし、日本では 78%の回答者が「完全に室内で飼養する」ことを選択するのに対し、英国では同回答を選択した回答者は 33%にとどまり、65%の人が「猫が屋外へ行ける」飼養方法を推奨することが分かりました。さらに、屋外に出ることによって猫が得る利益(猫らしい行動の発現など)とリスク(怪我など)について、日英ともに共通した認識を持っている一方、英国と比較して日本の回答者は、リスクをより強く意識していることが示唆されました(メイン画像)。
同様に、治癒の見込みのない病気に罹患した犬のシナリオを設定し、両国での安楽死の判断について調べました。その結果、同じ状況の犬に対して、日本では 5%の回答者が安楽死をするべきと判断したのに対し、英国では 40%の人が安楽死をするべきと考えることが分かりました。一方、日本においても、その犬の「痛みがコントロールできなくなったとき」及び「精神的ストレスが重篤になったとき」は、それぞれ 92%、85%の回答者が安楽死の判断をすると回答し(いずれも英国では約 100%の回答者が安楽死を選択)、安楽死によって苦痛を取り除くことは、日英に共通した理解であることが分かりました。他方で、その犬が「自分で歩くことができなくなったとき」など、犬自身の行動発現が制限される状況で両国の差が最も顕著となり、英国では 96%の回答者が安楽死をするべきと判断するのに対し、日本で安楽死を選択する人は 25%にとどまりました。さらなる解析により、英国においては、その犬にとって「自分自身で行動できないこと」が「精神的ストレス」と結び付けて考えられているのに対し、日本ではその関連・連想が弱いことが分かりました。
以上のことから、本研究を通じて日本と英国の獣医師・動物行動/福祉学研究者が有する、動物福祉の理解・解釈について一部を明らかにしました。動物福祉の考え方は英国が発祥ですが、動物の管理において、日本でも概ね同様の考え方や態度を持っていることが分かりました。一方、動物が「その動物らしい行動」を発現することについて日英で捉え方が異なり、日本ではその意義が重視されづらい傾向が可視化され、日本に特徴的な社会通念やリスクを忌避する性格などに起因する可能性が考えられました。
【今後への期待】
動物はそれぞれの種特異的な行動への欲求や動機を持っており、その行動を発現することは動物の身体的だけでなく精神的な健康にとって非常に重要です。本研究により、これからの日本における動物福祉の理解・普及において、動物の行動の意義や必要性を強調した教育や情報発信の重要性が示されました。
一方で、動物の飼養には文化や社会通念、さらに経済や地理、気候など様々な要因が影響し、「5 つの自由」すべてを平等に提供することが現実的ではない場合もあります。動物にとってより良い生活を提供することの重要性は自明ですが、持続可能性という観点から、私たち人間にとって無理のない共生のかたちも大切です。動物に対する考え方や関わり方は多様で感情的になり易い中、バランスの取れた議論には科学的データの蓄積が重要であり、本研究はその一助となる知見を提供しました。また、本研究は動物福祉への理解について「5 つの自由」に着目して国・文化間を比較した初めての研究であり、他文化との比較など、今後のさらなる発展が期待されます。
【謝辞】
本研究に参画し、貴重な意見をご共有くださった回答者の皆様に御礼申し上げます。また本研究は、JSPS 若手研究者海外挑戦プログラム、北大研究者海外派遣支援プログラム、JSPS 海外特別研究員、JSPS 科研費 JP23K05515 の助成を受けたものです。
■論文情報
論文名: Cross-cultural variation in understanding of animal welfare principles and animal management practices among veterinary and animal welfare professionals in the UK and Japan(日英の獣医師・動物福祉学研究者が有する動物福祉の原則及び管理方法に対する理解の文化差)
著者名 :大谷祐紀 1(研究当時),2(研究当時),3、金森万里子 4,5、加藤博美 6、Cathy Dwyer1,7(1 エジンバラ大学獣医学部、2 北海道大学大学院獣医学研究院、3 北海道 One Healthリサーチセンター、4 京都大学人と社会の未来研究院、5 ストックホルム大学公衆衛生科学部、6 農業・食品産業技術総合研究機構、7 スコットランド農学校動物獣医学部)
雑誌名 :Animal Welfare(動物福祉学の専門誌)
DOI: 10.1017/awf.2025.10026
公表日: 2025 年 8 月 6 日(水)(オンライン公開)
【参考図】
メイン画像:
伴侶動物にとって「最も重要な自由」として選んだ人の割合(回答者は複数の自由を選択可)。
下図:
日本と英国の獣医師・動物行動/福祉学研究者が推奨する猫の飼養方法と、その理解に影響する「5 つの自由」。
【用語解説】
*1 国際獣疫事務局(World Organization for Animal Health: WOAH) … 動物の感染症や衛生、福祉について取り決めやガイドラインを作成する国際機関。