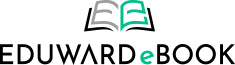図1:(左)小型のビデオカメラを装着したオオミズナギドリのイラスト (右)糞の瞬間の映像の切り抜き
寄稿者:東京大学
《発表のポイント》
◆海鳥の糞には栄養塩が豊富に含まれており、海洋の生態系において重要な役割を果たしていると考えられます。
◆本研究では、オオミズナギドリという海鳥の腹部にビデオカメラを装着して排泄腔のあたりを撮影し続けることで、糞をする頻度とタイミングを初めて調べました。排泄には正確な周期性があり、また海面に着水している間は糞をしないことが明らかになりました。
◆海鳥の排泄タイミングを明らかにすることで、海洋栄養塩の循環や鳥インフルエンザの感染経路をより深く理解することにつながると考えています。
《ニュース概要》
■ 概要
東京大学大気海洋研究所の上坂怜生特任研究員と佐藤克文教授は、動物装着型のビデオカメラを用いて、広大な海で生活する海鳥の排泄行動を記録・解析しました。海鳥の糞は、窒素やリンなどの栄養塩が大量に含まれているだけでなく、鳥インフルエンザウイルスなどの病原体を媒介する存在でもあります。しかし、広い海に生息する海鳥の排泄行動を直接観察し続けるのは困難なため、海鳥がどのような頻度とタイミングで糞をしているのかは不明でした。本研究チームはオオミズナギドリの腹部に小型ビデオカメラを装着して排泄腔の付近を撮影し続けるというユニークな方法でこの課題に取り組みました。
本研究でビデオカメラを装着したオオミズナギドリは、4~10分の間隔で糞をしており、正確な周期性を保って排泄を行っていました。また、ほぼすべての排泄が飛行中に行われており、着水中であってもわざわざ一度飛び立ってから海上に糞を落とすという特徴が確認されました。これらの知見は、海鳥が糞を通じて海洋に供給する栄養塩の量を評価するための重要な基盤になるほか、海上での鳥インフルエンザの感染経路をより詳しく知ることにもつながると考えています。
■ 発表内容
海鳥の糞は、肥料として使われることがあるほどたくさんの栄養が含まれています。たくさんの海鳥が繁殖のために一斉に集まる島では、糞によって土壌に多くの栄養が蓄積されることも知られています。しかしその一方で、海にいる間の海鳥の排泄パターンについては、空を飛んで移動する海鳥を継続的に観察し続けるのが難しいため、そのほとんどが謎に包まれていました。クジラの場合は、深い深度で餌を食べた後に海面付近で排出する糞や尿が海洋の栄養塩の鉛直循環を促進する役割を持っており、これはホエールポンプと呼ばれています。同じように、地球上に数億羽いる海鳥でも、彼らの糞には海洋生態系を構成する大事な役割があることが予想されます。また、近年では野生の海洋生物で鳥インフルエンザが急速に広まっています。感染の多くは糞を経由していると考えられているため、海鳥がどれくらいの頻度で、またどのようなタイミングで糞をするのかを調べることは非常に重要です。
本研究チームは、海鳥の中で最も個体数の多いミズナギドリ目(注1)に属する、オオミズナギドリの排泄行動を調べました。オオミズナギドリの腹部に後ろを向けた小型のビデオカメラを装着することで排泄腔の付近を撮影し続けるというユニークな方法によって、海上での排泄行動を記録しました(図1)。
15羽から収集した合計約36時間の映像の中で、オオミズナギドリは195回の排泄を行っていました。ほとんどの個体は4~10分程度の一定の間隔を保ったまま糞をしており、正確な周期性が見られました(図2)。これは、体内の消化物の量によって糞の頻度が徐々に変わるのではないかという、直感的な予想には反する結果です。ビデオの記録は長くても1個体あたり3時間程度であるため、この周期性がどれくらいの時間持続するのかを調べるためにもさらなる調査が必要です。また別の特徴として、ほぼすべての排泄が飛行中に行われており、着水中であってもわざわざ一度飛び立ってから海上に糞を落とすという様子が観察できました。今回確認した195回の排泄のうち着水中に行われたのは1度のみでした。これは、海鳥が飛び立つのに非常に体力を使うという背景を考えると、とても興味深い行動です。体に糞が付くのを避けたり、天敵をおびき寄せてしまうのを防いだりするのが目的ではないかと考えられますが、詳しい理由はよくわかっていません。
今回のデータを平均すると、オオミズナギドリは1時間当たり5.2回程度の頻度で糞をしていることが分かりました。陸上で計測した糞の重さを考慮すると、これは1時間当たり約30gの糞を海に落としていることになります。オオミズナギドリの体重は500g程度であり、この糞の量は体重の約5%に相当するため、飛行に必要なエネルギーにも排泄は関係していると考えられます。ただし、1度に排泄する糞の量には大きなばらつきがあったうえ、糞の重さは陸上と海上では異なると考えられるため、より正確な数値を求めるためには今後さらなる調査が必要です。
オオミズナギドリの排泄は、餌を採るために他の個体と集団を作っているときでも頻繁にみられました。そのため、海鳥の餌場となっている海域では、糞による局所的な栄養塩濃度の増加が起こっている可能性があります。また海鳥は、異なる繁殖地から来た個体が同じ餌場を利用することもあります。そのため、このような集団を作っている際に排泄が見られたことは、繁殖地間の感染症の拡大が海上で糞を媒介して起こっているという考え方を支持しています。
今回の研究は、沿岸を離れた海洋生態系における海鳥の糞の役割を解明するための最初の一歩であると言えます。今後は、海鳥全体が海に落とす糞の量をより正確に推定したり、排泄の観察を他の種類の海鳥へ広げたりすることで、海洋生態系の仕組みをより深く解明することにつながると期待されます。
■ 発表者・研究者等情報
東京大学 大気海洋研究所 海洋生命科学部門
上坂 怜生 特任研究員
佐藤 克文 教授
■ 論文情報
雑誌名:Current Biology
題 名:Periodic excretion patterns of seabirds in flight
著者名:Leo Uesaka*, Katsufumi Sato
DOI: 10.1016/j.cub.2025.06.058
URL: https://authors.elsevier.com/a/1ldGk3QW8SA3Oyこのリンクは別ウィンドウで開きます
■ 研究助成
本研究は、科研費「国際先導研究(課題番号:22K21355)」、「基盤研究(A)(課題番号:22H00422)」、「若手研究(課題番号:24K17159)」、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2108)、及び東京大学大気海洋研究所共同利用研究プログラムの支援により実施されました。
■ 用語解説
(注1)ミズナギドリ目
オオミズナギドリの属する海鳥の分類目であり、アホウドリのなかまなども含まれる。地球上に4億羽ほどの個体数がいると推定されている。
■ 問合せ先
東京大学 大気海洋研究所 海洋生命科学部門
特任研究員 上坂 怜生(うえさか れお)
E-mail:leo-u◎g.ecc.u-tokyo.ac.jp
東京大学 大気海洋研究所 海洋生命科学部門
教授 佐藤 克文(さとう かつふみ)
E-mail:katsu@aori.u-tokyo.ac.jp
図2:オオミズナギドリが糞をしたタイミングを表す時系列グラフ
15羽のオオミズナギドリから収取したデータのうちの5羽の例です。黒い点が排泄のタイミングを表しており、灰色の網掛け部分はオオミズナギドリが飛行中であることを表します。糞の間隔が長いがそれでも周期性が明確な個体(上から2番目)や、途中で周期が変わる個体(上から4番目)なども見られました。