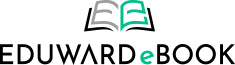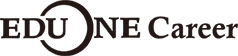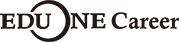寄稿者:京都大学
《ニュース概要》
■概要
「犬には人を見る目がある」とよく言われますが、犬が人間の行動を観察し評価しているかは、まだ明らかではありません。オーストリア・ウルフ・サイエンス・センターでの研究では、群れ飼育の犬やオオカミは人間についての評価を形成しないことが示されました。
本研究はウィーン獣医大学クレバー・ドッグ・ラボで実施されました。実験当時、同大学の博士課程に在籍し、現在は京都大学の特定研究員であるジム・ホイラム氏が中心となりました。
ペットの犬40頭を対象に、犬が気前のよい人(餌を与える)と利己的な人(与えない)を、他の犬のやりとりを観察する(いわゆる「傍観的観察」)と自ら体験する「直接的経験」から区別できるかを検証しました。犬が誰に先に近づくかや、親和的行動の時間を分析しました。
その結果、年齢にかかわらず、犬は特に気前のよい人を選ぶ傾向はなく、どちらの人を選ぶかは偶然の範囲内でした。飼い犬にとって、人を評価するのは予想以上に難しい可能性があります。
本研究成果は、2025年6月28日に国際学術誌「Animal Cognition」オンライン版に掲載されました。
1.背景
以前の研究では、オーストリアのウルフ・サイエンス・センターで群れで生活する犬やオオカミが、直接的または間接的な経験を通しても、人間に対して評判を形成しなかったことが示されました(Jim et al.,2022)。その一因として、これらの動物が人間との関わりの経験が限られていたことが考えられます。本研究では、同じ実験設定を用いてペットとして飼われている犬を対象に検証し、犬の年齢層が評判形成能力に影響を与えるかどうかを調べました。
2.研究手法・成果
「傍観的観察」(eavesdropping)条件では、犬たちは2人の人間が犬のデモンストレーターと関わる様子を観察しました。一方の人間は寛大でその犬に餌を与え、もう一方は利己的で餌を与えませんでした。「直接経験」条件では、犬たちはこの2人の人間とそれぞれ直接関わりました。犬たちの最初の選択および、各人間に対して示した親和的な行動(例:近づく、飛びつくなど)に費やした時間を分析しました。
その結果、すべての年齢層(若年、成犬、高齢犬)の犬たちにおいて、餌を与えた寛大な人間を利己的な人間よりも有意に好む傾向は見られず、傍観的観察または直接経験のいずれの後においても、彼らの行動は偶然の水準を上回りませんでした。
3.波及効果、今後の予定
本研究の結果は、犬のように人間と密接に協力する動物であっても、評価の形成はこれまで考えられていたよりも複雑である可能性を示唆しています。また、犬のこの能力を研究する際の方法論的な課題も浮き彫りになりました。たとえば、寛大な人と利己的な人という二者択一的なテストが本当に犬の理解を的確に捉えているかどうか、といった点です。
犬の社会的認知能力に影響を与える要因をより深く理解するために、今後の研究では、年齢や生活経験の異なる様々な犬(例:野良犬、介助犬、警察犬など)を対象に、系統的に比較することが求められます。
4.研究プロジェクトについて
本研究は、オーストリア・ウィーン獣医大学(University of Veterinary Medicine Vienna)メッサーリ研究所(Messerli Research Institute)の比較認知ユニットに所属するクレバー・ドッグ・ラボ(Clever Dog Lab)にて実施されました。研究当時、ジム・ホイラム氏は、同大学コンラート・ローレンツ動物行動学研究所(Konrad Lorenz Institute of Ethology)のドメスティケーション・ラボ(Domestication Lab)に所属する博士課程の学生でした。現在、同氏は京都大学 人と社会の未来研究院において特定研究員を務めています。オープンアクセスの公開にあたっては、ウィーン獣医大学から助成を受けています。また、本研究は、オーストリア科学基金(FWF)“DK Cognition and Communication 2”(Grant DOI: 10.55776/W1262:ジム・ホイラム、Friederike Range)による全額または一部の資金提供を受けました。さらに、本研究の一部は、日本学術振興会 科学研究費助成事業(科研費 23KF0113:ジム・ホイラム、山本真也)によっても支援されました。
■用語解説
・傍観的観察(eavesdropping):
自分は関わらず、他の人や動物のやりとりを見て情報を得ること。
■研究者のコメント
「今回の結果は、社会的評価が動物にとって難しい課題であることを示す研究に新たな知見を加えるものです。発達(年齢)が犬の社会的認知能力にどのように影響するかを明らかにするためには、野良犬、警察犬、介助犬など、異なる集団や経験を持つ犬を体系的に比較することが重要です。また、本研究は、現行の実験デザインには、犬の能力を十分に示すことを妨げる方法論的な限界がある可能性も示唆しています。人間と密接に協力する犬においても、人についての評価の形成はこれまで考えられていたよりも複雑であることが明らかになりました。」(ジム・ホイラム)
■論文タイトルと著者
タイトル:Do dogs form reputations of humans? No effect of age after indirect and direct experience in a food-giving situation(犬は人間の評判を形成するか?―間接および直接的な食物給餌経験の後も年齢による効果は見られず―)
著 者:Hoi-Lam Jim, Kadisha Belfiore, Eva B. Martinelli, Mayte Martínez, Friederike Range, & Sarah Marshall-Pescini
掲 載 誌:Animal Cognition
DOI:10.1007/s10071-025-01967-w
画像:研究者の愛犬ジャスパー(左)と親友サヒブ(右) 撮影:ジム・ホイラム