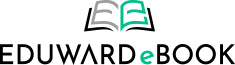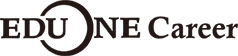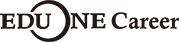寄稿者:群馬大学
《ニュース概要》
群馬大学生体調節研究所(群馬県前橋市)の、白川純教授、井上亮太助教らの研究グループは、国立国際医療研究センター、アルバータ大学(カナダ)等との共同研究で、糖尿病の治療に役立つ可能性のある重要な「代謝産物(体内で物質が変化してできる成分)」を発見しました。この代謝産物は、インスリンをつくる膵臓の細胞「膵β(ベータ)細胞」の増殖を助け、細胞死(アポトーシス)を防ぐ働きがあることが明らかになりました。
インスリンは、血糖値を下げる唯一のホルモンです。このインスリンをつくる膵β細胞は、膵臓の中にある「膵島」という組織にあります。膵β細胞が減少すると、インスリンが不足し、血糖値が高くなることで糖尿病の発症につながります。肥満などによってインスリンの効き目が弱くなる状態(インスリン抵抗性)では、体が血糖値を下げようとして膵β細胞の数を増やし、インスリンを補おうとします。しかし、糖尿病になると、この膵β細胞の増殖がうまくいかなくなったり、逆に細胞死によって数が減ってしまうことが、病気の発症や進行の大きな原因になると考えられています。そのため、膵β細胞を増やし、減少を防ぐしくみを明らかにすることは、糖尿病の根本的な治療につながると期待されています。
これまでの研究で、白川教授らの研究グループは、糖尿病治療薬「イメグリミン」に膵β細胞の増殖を促し、細胞死(アポトーシス)を防ぐ効果があることを発見してきました。今回の研究では、細胞内でのさまざまな代謝物質を網羅的に測定・解析する「メタボロミクス」という技術を用いて、イメグリミンによって変化する代謝物を詳しく調べました。その結果、インスリンをつくる膵β細胞の増殖促進や細胞死の抑制に関わる、特に重要な代謝産物として「アデニロコハク酸(Adenylosuccinate:S-AMP)」を特定しました。SAMPは、DNAを構成するプリン塩基という成分の中間的な代謝産物で、細胞の成長や再生に関わる重要な働きを持っています。
さらに、S-AMPの材料となるアスパラギン酸やイノシトールリン酸、またS-AMPをつくる酵素であるアデニロコハク酸合成酵素(Adss)も同時に増えていることがわかりました。これにより、S-AMPが体内で積極的につくられていることが示されました。
本研究により、S-AMPという代謝産物が、増殖の促進やアポトーシスの抑制を介して膵β細胞の量を増やすことが明らかになりました。今後、S-AMPがどのように働くのかを詳しく調べることにより、膵β細胞を回復させる糖尿病治療への応用が期待されます。
本研究の成果はDiabetes誌(American Diabetes Association:米国)に掲載されました。
1.本件のポイント
・インスリンをつくりだす膵β細胞の数(量)が不足することが糖尿病発症や進行につながる。
・膵β細胞の増殖を促しアポトーシスを防ぐことが、膵β細胞を増やす治療につながる。
・糖尿病治療薬のイメグリミンにより膵β細胞が増える際の代謝産物を同定した。
・そのうちアデニロコハク酸(S-AMP)が重要な役割を果たしていた。
・S-AMPが膵β細胞の量を回復させる糖尿病治療の鍵となる可能性が示された。
2.本件の概要
現在、日本では成人のおよそ4人に1人が糖尿病、またはその予備群であるとされており、糖尿病は「国民病」ともいえるほど身近な病気です。糖尿病は、血糖値を下げる働きを持つホルモン「インスリン」の分泌量や効果が不足することで、血糖値が慢性的に高くなる病気です。インスリンは、膵臓の中にある「膵島(すいとう)」という組織に存在する「膵β(ベータ)細胞」によって作られています。糖尿病の人では、この膵β細胞の数が減ることで、インスリンが十分に作られなくなってしまうことが、病気の発症や進行の原因の一つと考えられています。
通常、膵β細胞は、肥満などによってインスリンの効きが悪くなった場合(インスリン抵抗性)に、より多くのインスリンを作ろうとして細胞分裂を行い、自らの数を増やす仕組みが備わっています。しかし、長く続く高血糖や、血液中の脂肪酸の増加、体内の慢性的な炎症などの影響で膵β細胞に負担がかかると、細胞が自ら死んでしまう「アポトーシス(細胞死)」が進んでしまいます。このように、膵β細胞の数がうまく増えなくなったり、逆に減ってしまうことで、インスリンの供給が間に合わず、糖尿病の発症や悪化につながります。したがって、膵β細胞の「増殖を促す」と同時に「アポトーシスを抑える」ことができれば、糖尿病の新たな治療法として大きな可能性があると考えられます。さらに、自分の免疫で膵β細胞が破壊されてしまう1型糖尿病でも、わずかに膵β細胞が膵臓の中に残っており、体の中で膵β細胞を再び増やすことができれば、インスリンの産生を回復させることが期待されています。
糖尿病治療薬の一つであるイメグリミンは、膵β細胞からのインスリン分泌を増やすだけでなく、肝臓や筋肉におけるインスリンの効きを良くすることで、血糖値を下げる働きがあるとされています。2022年には、白川純教授らはイメグリミンが膵β細胞の増殖を促し、アポトーシスを防ぐ作用があることを報告しましたが、なぜそのような働きが起きるのか、その仕組み(メカニズム)は不明でした。
細胞は、外から取り入れた糖やアミノ酸、脂質などの栄養素を分解・利用する「代謝」という反応を行い、エネルギーや必要な物質を作り出しています。この過程で生まれる様々な物質を「代謝産物」と呼びます。代謝産物は、細胞の状態を反映する重要な指標であり、遺伝子やタンパク質の変化よりも直接的な影響を示すことがあります。そこで本研究では、「メタボロミクス」という技術を用いて、膵β細胞を含む膵島における代謝産物を網羅的に調べました。その結果、イメグリミンによって膵β細胞の増殖が進み、アポトーシスが抑えられている状態において、変化している特定の代謝産物を同定することができました。
なかでも注目されたのが、「アデニロコハク酸(Adenylosuccinate:S-AMP)」という代謝産物です。S-AMPはDNAを構成する物質のもとになるアデニンという成分の中間代謝物であり、細胞の成長や増殖に関わると考えられています。さらに、このS-AMPの材料となるアスパラギン酸やイノシトールリン酸も同時に増加していることがわかりました。時間ごとに代謝物の変化を追っていくと、S-AMPが増える前に、アスパラギン酸やイノシトールリン酸の増加が先行して起こっていることが分かりました。また、S-AMPをつくる酵素であるアデニロコハク酸合成酵素(Adss:Adenylosuccinate synthetase)の遺伝子やタンパク質の量も、イメグリミン投与時に増えていることが確認されました。
そこで、S-AMPが本当に膵β細胞の増殖やアポトーシスの抑制に関わっているのかをさらに詳しく調べました。S-AMPの合成を妨げる薬剤であるアラノシンをマウスの膵島に使うと、イメグリミンによって得られていた膵β細胞の増殖促進やアポトーシス抑制の効果が見られなくなりました。この現象は、膵島移植に用いられるヒト膵島、再生医療に用いられるヒト多能性幹細胞由来膵島、さらには異種移植の研究に用いられる幼若ブタ膵島においても確認されました。また、マウスの膵島を使った実験では、アデノウイルスベクターを用いて、遺伝子のノックダウンという手法で、S-AMPを作り出す酵素の遺伝子の働きを弱めたところ、膵β細胞の増殖が減少し、逆にアポトーシスが増えることが確認されました。一方で、同じ酵素をアデノウイルスベクターで通常よりも多く作らせた(過剰発現させた)場合には、膵β細胞の増殖が促進され、アポトーシスが抑えられるという結果が得られました。
このように、イメグリミンという既に臨床で使用されている安全性の高い薬剤を用いて、S-AMPという代謝産物が膵β細胞の数を増やすしくみに関わっていることを突き止めた本研究は、安全で新しい糖尿病治療法の開発につながる可能性があります。今後は、S-AMPがどのようにして膵β細胞に働きかけるのか、その詳細な仕組みをさらに明らかにすることで、糖尿病に対する新しい治療法の確立が期待されます。
本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業、科学研究費助成事業、および民間助成金からの助成に加え、1型糖尿病の患者及び家族による認定NPO法人であるIDDMネットワークの支援を受けて行われました。
3. 関連リンク
・群馬大学生体調節研究所
https://www.imcr.gunma-u.ac.jp/
・生体調節研究所代謝疾患医科学分野
https://diabetes.imcr.gunma-u.ac.jp/
4.論文詳細
論文名:Adenylosuccinate mediates imeglimin-induced proliferative and antiapoptotic effects in β-cells.
論文著者:井上亮太(1), 都野貴寛(1), 西村隆史(2), 福島説子(1), 平井 さやか(3), 霜田雅之(3), 吉成祐人(2), 酒井智里(1), Tatsuya Kin(4), Euodia Xi Hui Lim(5,6), Adrian Kee Keong Teo(5,6),松本慎一(3), A. M. James Shapiro(4), 白川 純(1,7,*)
(1. 群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野、2. 群馬大学生体調節研究所個体代謝生理学、3.国立国際医療研究センター膵島移植企業連携プロジェクト、 4. アルバータ大学臨床膵島研究室、5. Stem Cells and Diabetes Laboratory, Institute of Molecular and Cell Biology(IMCB), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)、6. Departmentof Biochemistry, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore、7. 横浜市立大学医学部分子内分泌・糖尿病内科、*責任著者)
掲載誌:Diabetes誌(American Diabetes Association:米国)
公開日:2025年7月10日