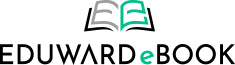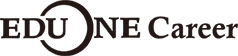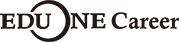寄稿者:岐阜薬科大学
《ニュース概要》
■概要
フェロトーシスとは二価鉄によって脂質膜やオルガネラ膜が酸化的に損傷されることで起きる細胞死であり、神経変性疾患や虚血性再灌流障害など多様な病態に関連することからことから近年非常に注目されている治療標的です。しかしながら、これまでに開発されてきたフェロトーシスの阻害剤のほとんどが鉄キレート剤とラジカルトラップ剤の2分類であり、これら阻害剤には鉄欠乏性貧血や肝毒性などの潜在的なリスクが存在するため、異なる阻害機序を有するフェロトーシス阻害剤の開発が求められています。
当研究室ではこれまでに第三級アミンオキシド(N-オキシド)が二価鉄により選択的に脱酸素化されことを利用し、二価鉄選択的検出プローブの開発を行ってきました。本研究では、このN-オキシド構造が二価鉄の選択的な酸化剤として機能することに着目し、フェロトーシスの発生要因となる二価鉄を酸化的に枯渇させることができれば新規フェロトーシス阻害剤として応用できると考えました。
まずN-オキシド型蛍光プローブの一つであるSiRhoNox-1(図1a)を用いてエラスチン誘導性フェロトーシスに対する阻害効果の評価を行いました。その結果、SiRhoNox-1によって細胞生存率が回復し、、その効果はフェロトーシス阻害剤として知られている鉄キレート剤(デフェロキサミン)と同等の阻害効果を示しました(メイン画像b)。
次に当研究室でこれまでに開発してきたNオキシド型二価鉄・ヘム検出プローブ群を用いて、エラスチン誘導性フェロトーシスに対する阻害効果を評価したところ、興味深いことに、阻害効果がプローブがどの細胞内小器官に集積するかによって大きく異なることがわかりました(下図a)。小胞体やリソソームに集積するプローブでは阻害効果が高く、一方でミトコンドリアや細胞外膜に集積するプローブでは阻害効果が見られませんでした。またヘムにのみ応答するプローブも同様に阻害効果が確認できませんでした。これらの結果から、エラスチン誘導性フェロトーシスの発生に関与する二価鉄は主に小胞体やリソソーム由来である可能性が示唆されました。フェロトーシスの発生場所は未だ不明な点が多くあり、さまざまな手法によってその同定が進められてきました。その中で、私たちの研究成果はフェロトーシスの根幹となる二価鉄の場所からその発生場所を示唆する初の報告です。
次に異なる作用機序のフェロトーシス誘導剤(RSL3、FINO2、FIN56)を用いてN-オキシド型プローブによる阻害効果を評価したところエラスチンと同様に阻害効果が確認されました。その一方で、アポトーシス誘導剤(スタウロスポリン、ロテノン)やネクローシス誘導剤(過酸化水素)に対しては一切阻害効果を示しませんでした。この結果をもとに作成したヒートマップから、N-オキシド型プローブはフェロトーシスに対して選択的な阻害効果を有することがわかりました(下図b)。
本研究成果はフェロトーシスに寄与する二価鉄の細胞内分布を示すだけでなく、フェロトーシス関連性疾患に対する新たな治療戦略になると期待できます。
本研究成果は、岐阜薬科大学ケミカルバイオロジー研究室の河合 寛太氏(大学院博士課程学生)、永澤 秀子 特任教授、平山 祐 教授らにより英国王立化学会(Royal Society of Chemistry)学会誌の「Chemical Science」に公開されました。また、河合氏が描いた絵が論文の表紙として採用されました。
■本研究成果のポイント・今後期待される成果
これまで二価鉄の蛍光検出に使用してきた化合物が、新たな細胞死:フェロトーシスの阻害薬になることを見出した。
これらの化合物の構造をもとに、フェロトーシスの関わる疾患に対して、新たな治療薬への展開が期待される。
■論文情報
雑誌名:Chemical Science
論文名:Inhibition of ferroptosis by N-oxide-based fluorescent probes via selective oxidation of ferrous ions
著者:Kanta Kawai, Rie Haruki, Shunsuke Nozawa, Hideko Nagasawa, Tasuku Hirayama
DOI番号:10.1039/d4sc07972h
Cover artとして採用されました。