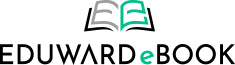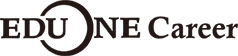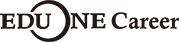寄稿者:京都大学
《ニュース概要》
■概要
ネコ(Felis catus)は祖先種のリビアヤマネコ(Felis lybica)から家畜化される過程で、さまざまな社会的行動を示すようになりました。行動特性には、育った環境だけでなく、生まれつきの遺伝的要因も関与しています。ネコと同じく伴侶動物のイヌでは、多くの研究から遺伝子と行動特性との関係が明らかになってきましたが、ネコの研究は少なく、まだ分かっていないことが多くあります。
そこで、京都大学野生動物研究センターの村山美穂教授、京都市立芸術大学の服部円講師、京都大学理学研究科の岡本優芽博士後期課程学生らは、家庭で飼育されているネコを対象に行動特性とアンドロゲン受容体遺伝子の関係を調べました。その結果、この遺伝子のタイプによって、ゴロゴロ音や鳴き声、見知らぬ人への攻撃性といった行動特性に違いが見られることが明らかになりました。さらに、他のネコ科動物種と比べたところ、ネコだけに見られる遺伝子型があることが分かり、家畜化の過程で変化が起こった可能性があると考えられました。将来的には、個体ごとの行動特性に合わせた環境づくりなど動物福祉にも役立てられると期待されます。
本研究は、全国のネコの飼い主様とご愛猫のご協力のもと実施しました。本研究の成果は、2025年5月28日に国際学術誌「PLOS One」にオンライン掲載されました。
1.背景
ネコは人気の高い伴侶動物です。祖先種のリビアヤマネコから形態はあまり変わらず依然として肉食動物の特徴を有しますが、行動は大きく変化しました。祖先種を含め、ネコ科動物種の多くは単独性ですが、ネコは社会性が見られ、他個体やヒトと一緒に生活することができ、様々なコミュニケーションも行います。
行動特性には、環境要因に加えて遺伝的要因も深く関与しています。イヌなどの他種ではゲノムワイド関連解析など大規模なものを含む様々な研究が行われており、行動特性と関連する遺伝子が複数報告されてきました。しかし、ネコではこうした研究はあまり進んでいません。本研究では、ネコの行動特性の遺伝的背景を調べるために、アンドロゲン受容体遺伝子に着目しました。この遺伝子は、テストステロンなどのアンドロゲンに高い親和性をもつ受容体をコードします。この遺伝子の一部の長さには個体差が見られ、これが行動特性と関連するということがヒトやイヌなどの研究を通して分かってきました。ネコにおいても遺伝子の個体差が見られることは報告されていますが、この違いと行動特性との関連は未解明でした。そこで本研究では、ネコのアンドロゲン受容体遺伝子と行動特性との関連を明らかにすることを目的としました。
2.研究手法・成果
家庭で飼育されているネコ280個体(すべて雑種、避妊去勢済)を対象に、質問紙を用いて行動特性の評定を行いました。また、DNAも採取し、アンドロゲン受容体遺伝子を解析しました。その結果、短いタイプの遺伝子を持つネコは、長いタイプの遺伝子を持つ個体より、「ゴロゴロいう」傾向が高いことが分かりました。特にオスでは、コミュニケーションや要求に関連する「特定の鳴き声/発声」のスコアも高いことが分かりました。このことから、この遺伝子が音声コミュニケーションと関わっている可能性が示唆されました。一方メスでは、短いタイプの個体の方が「見知らぬ人への攻撃」のスコアが高いことも分かりました。
さらに、トラなど他のネコ科動物11種と比較したところ、ネコに系統的に最も近い、ベンガルヤマネコやスナドリネコ(いずれもベンガルヤマネコ系統)は、短いタイプしか持っていないことが確認されました。他のネコ科動物種よりもネコが長かったことから、家畜化による遺伝子の変化と関わる可能性があります。
3.波及効果、今後の予定
本研究より、ゴロゴロ音を発する傾向が高いネコは、アンドロゲン受容体遺伝子が短い傾向にあることが分かりました。他のネコ科動物種も、多くが短いタイプの遺伝子を有していました。これまでの研究から、ネコの中でも特に純血種のネコは、雑種に比べて長いタイプの遺伝子を持つ割合が高いと報告されています。本研究に参加した多くのネコが元野良で、野外で生活していた後に保護された個体であったことに対し、純血種の多くは生まれた時からヒトによる保護がある環境で育ちます。ゴロゴロ音は、ネコ同士のコミュニケーションにおいて親和の表現や、子ネコが母ネコの注意を引いて世話を促す手段として用いられるなど、生存に重要な役割を果たしていることが知られています。生後すぐにヒトが世話をする場合は、こうした生存のための音声コミュニケーションの必要性が低くなると予想されるため、ヒトとの関わりが遺伝子の頻度の違いにつながっている可能性があります。
今後は、ヒトとの関係を通してネコに起こった行動特性の変化をより深く理解するため、さまざまなネコの品種や、他のネコ科動物種に広げて比較を行い、研究を進めていく予定です。さらに、遺伝子から行動特性を推測することができるようになれば、飼育環境を個体に合わせて整えることができ、ネコだけでなく直接の観察が難しい野生ネコ科動物種にも応用し、動物福祉に役立てられる可能性があります。
4.研究プロジェクトについて
本研究は、独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)、日本学術振興会、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)次世代研究者挑戦的研究プログラムの助成を受けて実施されました。
■用語解説
・アンドロゲン
雄の生殖系や二次性徴の発達や維持を刺激するテストステロンなどのステロイドホルモンの総称。
■研究者のコメント
「ネコは私たちにとって非常に身近な存在ですが、実はまだ分かっていないことも多いため、もっと知りたいと思い研究を始めました。ネコの情報を集めるために飼い主様にご協力を依頼したところ、全国各地から265名もの方がご参加くださいました。多くの貴重なデータが集まり、また応援メッセージもいただくことがあり、嬉しくなると同時にネコ研究への関心の高さを実感しました。調べれば調べるほど奥深い行動特性の研究を通して、ネコへの理解を深め、ネコとヒトがお互いにもっと幸せに暮らせる関係づくりに繋げられればと思い、日々取り組んでいます。」(岡本優芽)
■論文タイトルと著者
・タイトル
Association between androgen receptor gene and behavioral traits in cats (Felis catus)
(ネコのアンドロゲン受容体遺伝子と行動特性の関連)
・著者
Yume Okamoto, Madoka Hattori, Miho Inoue-Murayama
・掲載誌
PLOS One
・DOI
10.1371/journal.pone.0324055
■詳細はこちら※参照元のサイトを開きます
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2025-05-29-0
メイン画像:研究に参加してくださったご愛猫(撮影:飼い主様)
下図:「ゴロゴロいう」のスコアとアンドロゲン受容体遺伝子のタイプ