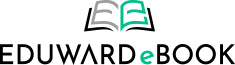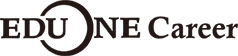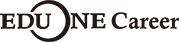寄稿者:高知大学/鹿児島大学
《ニュース概要》
【ポイント】
・アミノ酸には、L 体と D 体という2種類の鏡像異性体が存在し、地球上の生物のタンパク質は主に L 体のアミノ酸で構成されている。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)等が開発したキラル誘導体化 LC-TOF/MS法は、D/L-アミノ酸を精確に識別し、高感度で検出できる化学分析法である。
・この分析法によって、食肉処理直後と熟成後の牛の筋肉組織から D-セリン、D-アスパラギン酸、D-スレオニンを検出することに成功した。
・特に D-スレオニンは、動物の筋肉組織からは世界で初めて検出された。
【概要】
高知大学(松川和嗣准教授)、鹿児島大学(室谷進教授)、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(HMT)で構成する共同研究チームは、牛肉の品質やおいしさの理解を深める可能性のある重要な低分子化合物を検出しました。
私たちの体を作るタンパク質の多くは L-アミノ酸からできていますが、自然界には鏡像異性体の関係にある D-アミノ酸*1もごく微量ながら存在し、その多様な働きが注目されています。研究チームは、これまでほとんど知見がなかった牛肉中に含まれる D-アミノ酸について、本格的な調査を行いました。
近年に開発された高感度な化学分析技術(キラル誘導体化 LC-TOF/MS 法*2)を用いることで、牛肉の筋肉(生体と同等な食肉処理直後のものと、7日間熟成させたもの)から、Dセリン (D-Ser) 、D-アスパラギン酸 (D-Asp)、そして D-スレオニン (D-Thr) という3つの主要な D-アミノ酸を精確に識別して検出することに成功しました。特に、D-Thr が動物の筋肉組織で確認されたのは世界で初めてです。この発見は、牛の体の仕組みや牛肉の品質について、より深く理解するための重要な手がかりとなります。
今後、これらの D-アミノ酸が牛の体内でどのように蓄積され、具体的にどのような働きをしているのか、さらなる研究が進められることで、将来的にはより高品質でおいしい牛肉の開発などへの貢献が期待されます。
この研究成果は、令和7年5月 10 日付(日本時間 22 時 35 分)国際的な学術雑誌「Journalof Food Composition and Analysis」に掲載されました。
【研究の背景】
私たちの体や他の哺乳動物の組織では、アミノ酸の一種である D-アミノ酸が、免疫機能や脳の神経伝達といった重要な生理機能に関わっていることが知られています。しかし、私たちが日常的に食べる牛肉などの家畜の筋肉(骨格筋)に、D-アミノ酸がどの程度含まれ、どのような役割を果たしているのかについては、まだ多くが謎に包まれていました。過去の研究では、加熱処理されたハム(豚肉)から D-アミノ酸が検出された例があり、牛肉にも Dアミノ酸が存在し、その品質や風味に影響を与えている可能性が考えられていました。
そこで本研究では、この未解明な点を明らかにするため、高感度な分析技術であるキラル誘導体化 LC-TOF/MS 法を用いました。そして、和牛の2品種(黒毛和種および褐毛和種高知系)から得た僧帽筋(体内の筋肉の一部)と、そこから培養した細胞を試料としました。これらの試料について、食肉処理直後(新鮮で生体と同等な状態)と、食肉処理後7日間熟成させた時点での、D-アミノ酸および L-アミノ酸の種類と量を詳しく比較調査しました。
【研究の目的・内容・成果】
本研究では、新たに開発した高精度に D/L アミノ酸を識別するキラル誘導体化法により、牛の筋肉(僧帽筋)を処理し、高感度な LC-TOF/MS 法で D-アミノ酸を網羅的に検出しました。その結果、牛の筋肉中で少なくとも D-Ser、D-Asp、D-Thr を検出することに成功しました (下図)。このうち D-Thr が動物の筋肉組織に存在することを、世界で初めて明らかにしました。
【成果の意義/今後の展望】
本研究は、牛肉中の D-Thr の存在を明らかにした最初の研究です。
D-Ser および D-Asp は、熟成前後の牛肉および同じ部位から培養した細胞から検出されました。一方、D-Thr は牛肉からは検出されたにもかかわらず、培養細胞からは検出されていません。このことは、筋肉組織で検出された D-Thr が、牛体の筋肉組織外または牛自身ではないルーメン細菌に由来する可能性を示唆しています。
また、牛肉の美味しさに関与するアミノ酸の中には、L 体と D 体で味覚が異なることが知られており (例えば、L-グルタミン酸は旨味ですが、D-グルタミン酸は酸味)、高感度な化学分析によって食品の美味しさをより詳細に解析することができます。
今後、本研究をさらに発展させることで、D/L アミノ酸の生理学的特性と牛肉の品質の理解が深まることが期待されます。
【論文情報】
・掲載雑誌
Journal of Food Composition and Analysis
・URL
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088915752500537X?via%3Dihub
(5月10 日午後 22 時以降公開)
・論文名
Chiral derivatization LC-TOF/MS analysis reveals presence of D-amino acids in bovineskeletal muscle tissue and the cultured cells
・DOI
https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.107722
・著者
吉國美咲妃(高知大学)、井口和樹(HMT)、乙黒靖裕(HMT)、佐藤俊(HMT)、長井宏賢(高知大学)、竹村泰雄(高知大学)、坂野新太(高知大学)、樋口琢磨(高知大学)、坂本修士(高知大学)、室谷進(鹿児島大学)、松川和嗣(高知大学)
【用語解説】
注 1) D-アミノ酸
アミノ酸には L 型と D 型という鏡像関係にある立体異性体が存在し、自然界のタンパク質を構成するのは主に L-アミノ酸です。D-アミノ酸は微生物や一部の動物の体内に微量に存在し、特有の生理機能を持つことが近年明らかになってきています。
注 2) キラル誘導体化 LC-TOF/MS 法
アミノ酸の L 型と D 型を区別するために特殊な試薬で処理(誘導体化)し、液体クロマトグラフィー飛行時間型質量分析計(LC-TOF/MS)で分離・検出する分析手法です。
■詳細はこちら※参照元のサイトを開きます
https://www.kochi-u.ac.jp/information/2025052300012/file_contents/file_20255235103836_1.pdf
メイン画像:研究の対象とした黒毛和種 (左)および褐毛和種高知系 (右)
黒毛和種は、全国で普及している和牛品種。褐毛和種高知系は「土佐あかうし」と呼ばれ、高知県で独自に改良された希少品種で、高知大学では約 90 頭を飼養している。
下図:分析結果の一例 誘導体のクロマトグラム