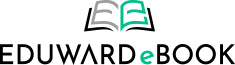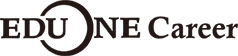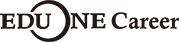寄稿者:東邦大学
《ニュース概要》
東邦大学薬学部薬理学教室の小原圭将准教授、吉岡健人講師、田中芳夫教授らの研究グループは、米ぬかや穀類に含まれる天然成分「フェルラ酸(FA)」に、腸の筋肉の収縮を抑える作用があることを発見しました。さらに、この抑制作用は、主に電位依存性カルシウムチャネル(VDCC)(注1)を介したカルシウムイオン(Ca2+)の流入の抑制によって生じることを突き止めました。この研究成果は、消化管の過活動が関与する過敏性腸症候群(IBS)(注2)などの予防・改善に貢献する可能性があり、今後の応用が期待されます。
この研究成果は、学術雑誌「Journal of Pharmacological Sciences」に2025年5月20日に公開されました。
■発表者名
小原 圭将(東邦大学薬学部薬理学教室 准教授)
吉岡 健人(東邦大学薬学部薬理学教室 講師)
田中 芳夫(東邦大学薬学部薬理学教室 教授)
■発表のポイント
腸の過剰な収縮は、腹痛や下痢などの症状を伴うIBSなどの疾患に深く関係しています。
フェルラ酸は、モルモットの小腸(回腸)の平滑筋を用いた実験において、アセチルコリン、ヒスタミン、セロトニン、プロスタグランジンF2αなどによって引き起こされる収縮を濃度依存的かつ可逆的に抑制することが確認されました。
この収縮抑制作用は、主に筋肉細胞へのCa2+の流入を担うVDCCの遮断によるものであり、作用は各種腸管収縮物質に対して非競合的(注3)に発現しました。
フェルラ酸は穀類に含まれるポリフェノールであり、食品やサプリメントとして既に広く利用されていることから、腸管機能を調節する機能性成分としての応用が期待されます。
■発表内容
フェルラ酸は、植物由来のポリフェノールの一種であり、特に米ぬかや小麦の外皮などに豊富に含まれています。これまでに、抗酸化作用、抗炎症作用、血管内皮保護作用、さらにはアルツハイマー病などの神経変性疾患に対する神経保護効果など、多彩な薬理作用が報告されてきました。しかし、腸の運動に対する直接的な影響については十分に検証されていませんでした。
研究グループは、腸の運動を制御している平滑筋に対するフェルラ酸の影響を明らかにするため、モルモットの小腸(回腸)の平滑筋を用いた検討を行いました。その結果、フェルラ酸は、アセチルコリン、ヒスタミン、セロトニン、プロスタグランジンF2αなどの収縮因子によって引き起こされる回腸の収縮を、濃度依存的かつ可逆的に抑制することを示しました。また、各種収縮因子による回腸の収縮に対するフェルラ酸の抑制効果を解析した結果、その作用が非競合的な阻害作用であることも明らかとなりました。これは、フェルラ酸が特定の受容体を直接ブロックするのではなく、共通の細胞内経路に作用することで収縮全体を抑えていることを意味します。実際に、脱分極によってVDCCを活性化させる高濃度カリウム刺激による収縮に対しても、フェルラ酸は抑制効果を示しました。また、ラット大動脈由来のA7r5細胞における細胞内Ca2+濃度測定実験においても、フェルラ酸がVDCC活性化を介した細胞内のCa2+濃度の上昇を抑制することが確認されました。以上の結果から、フェルラ酸の腸管の収縮に対する抑制作用は、主にVDCCを介したCa2+の流入の抑制によって生じることを突き止めました。
フェルラ酸は食品由来で安全性が高く、すでにサプリメントなどにも利用されている成分です。今回の成果は、下痢型IBSなどの腸運動異常に対する、フェルラ酸の非薬物的な補助療法への応用の可能性を示すものです。一方で、便秘型IBSや健常者では腸の運動を過度に抑える懸念もあるため、今後は摂取対象・用量・使用条件の最適化など、ヒトを対象とした検証が必要とされます。
■発表雑誌
雑誌名:「Journal of Pharmacological Sciences」(2025年5月20日)158巻4号、289-293
論文タイトル:Ferulic acid suppresses guinea pig ileal longitudinal smooth muscle contractions by inhibiting voltage-dependent Ca2+ channels
著者:Keisuke Obara, Kento Yoshioka, Aya Shimada, Sakika Ichihara, Wakaba Kinami, Futaba Makino, Naho Takazakura, Miwa Enomoto, Yoshio Tanaka
DOI番号:10.1016/j.jphs.2025.05.012
論文URL:https://doi.org/10.1016/j.jphs.2025.05.012
■用語解説
(注1)電位依存性カルシウムチャネル(VDCC:Voltage-Dependent Calcium Channel)
筋肉が収縮するためには、細胞の外からカルシウムイオン(Ca2+)が中に流れ込む必要があります。電位依存性カルシウムチャネルはその“入り口”として働く重要なタンパク質で、電気的な刺激(膜電位の変化)によって開閉が制御されています。心臓や血管、消化管などの平滑筋でも中心的な役割を担っており、これをブロックすることで筋収縮を抑えることができます。高血圧の治療薬である「カルシウム拮抗薬」もこのチャネルを標的としています。
(注2)過敏性腸症候群(IBS:Irritable Bowel Syndrome)
腸に炎症や潰瘍などの器質的な異常が見られないにもかかわらず、慢性的な腹痛や下痢・便秘などの症状が続く機能性消化管障害のひとつです。症状のタイプは人によって異なり、「下痢型」「便秘型」「混合型」などがあります。ストレスや自律神経の乱れが関与しているとされ、現代人に増加傾向にある疾患です。明確な治療法がないことから、症状をコントロールするための新しい選択肢が求められています。
(注3)非競合的作用
受容体拮抗薬の作用には「競合的」と「非競合的」があります。競合的とは、薬が受容体の鍵穴に入り込んで、他の物質(たとえばアセチルコリンなど)が作用するのを邪魔するタイプのことを言います。一方、非競合的作用は、その受容体ではなく、別の場所(細胞の内部の仕組みや通路など)に働きかけて刺激物質による作用を抑える作用です。今回のフェルラ酸は、刺激物質の受容体そのものには直接関与せず、主に細胞内のカルシウム流入を抑えることで収縮を弱めています。
■詳細はこちら※参照元のサイトを開きます
https://www.toho-u.ac.jp/press/2025_index/20250523-1493.html