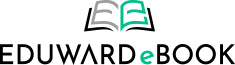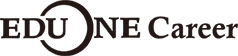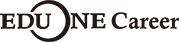寄稿者:慶應義塾大学
《ニュース概要》
慶應義塾大学医学部内科学教室(呼吸器)の安田浩之准教授、篠崎太郎助教(研究当時、現在は東京医療センターに出向)、外科学教室(呼吸器)の浜本純子助教、医化学教室の佐藤俊朗教授らの研究チームは、肺がん患者から臓器のミニチュアである肺がん「オルガノイド」(注1)の樹立に成功し、抗がん剤(EGFR(注2)チロシンキナーゼ阻害剤:EGFR-TKI)治療後の再発の原因を突き止めるとともに、再発後に有効な可能性のある薬剤を同定しました。
肺がんはがん細胞が持つ遺伝子の異常(遺伝子変異)のタイプに応じて、いくつかのグループに分類されます。その中でEGFR遺伝子変異陽性肺腺がんは、肺がんの2-3割程度を占める最大のグループです。これらに対して、複数のEGFR-TKIが開発され、臨床現場で広く使用されています。ただ、その効果は永遠ではなく、多くの場合1-2年で薬が効かなくなり、再発を認めます。再発後の肺がんに対しては有効な薬剤が限られ、多くの患者が再発後1-2年で死亡に至ります。さらに、EGFR-TKIが効かなくなり再発する原因(耐性化機序)の究明が進められていますが、最も広く使用されるオシメルチニブ(タグリッソ🄬🄬)においては、再発症例の約半数で原因がわからない状態が続いています。このため、耐性化機序の解明と、その後の治療法開発が大きな課題となっています。
研究チームは、EGFR-TKI治療後の再発の原因を明らかにするため、EGFR遺伝子変異陽性肺腺がん患者の治療前及び治療後(再発後)のがん組織から合計39種類のオルガノイドを樹立しました。それらを用いた解析で、治療後の約4分の1の症例で「肺腺がん」(注3)と「肺扁平上皮がん」(注4)の特徴を併せ持つ「ハイブリッドタイプ」が出現することを世界で初めて見出しました。今までの研究で、肺がんのタイプが「腺がん」から「扁平上皮がん」に変わることで再発することは知られていましたが、ハイブリッドタイプによる再発は知られていませんでした。さらに研究チームは、これらハイブリッドタイプの肺がんにCDK4/6阻害薬の薬剤が有効である可能性を見出しました。今回の研究成果は、EGFR-TKIが効かなくなり再発した肺がんに有効な治療法の開発に役立つことが期待できます。本研究成果の詳細は、2025年5月11日(英国時間)に英科学誌Nature Communications(電子版)に掲載されました。
1.研究の背景と概要
肺がんは、日本においても世界においてもがん死因一位の疾患です。日本では、年間約13万人の肺がん患者が新規に発生し、約7万人が死亡しています。肺がんの中で、EGFR遺伝子変異を有する肺腺がん(EGFR遺伝子変異陽性肺腺がん)は、肺がん全体の2-3割を占め、最大のサブグループを形成しています。これらに対しては、EGFRの働きを抑えるEGFR-TKIが複数の製薬企業から開発されてきました。近年は、第三世代EGFR-TKIであるオシメルチニブ(タグリッソ🄬🄬)が優れた有効性と少ない副作用から広く使用されています。これらEGFR-TKIの有効性は高く、治療によって約8割の患者で腫瘍の速やかな縮小を認めます。しかし、この有効性も永遠ではなく、多くの場合1-2年で肺がんが再発します。いったん再発するとその後は有効な治療方法が限られ、多くの患者が再発後1-2年で死亡します。
このため、EGFR-TKIが効かなくなり再発する原因(耐性化機序)の解明と、耐性化を克服する治療法開発が大きな課題となっています。この問題を解決するため、世界中の多くの研究室で再発の原因の探索が行われてきましたが、最も広く使用されるオシメルチニブ(タグリッソ🄬🄬)においては、再発症例の約半数で原因がわからない状態が続いていました。
2.研究の成果と意義・今後の展開
主要な発見:
1)EGFR-TKI治療前後の検体から肺がんオルガノイドを樹立
研究グループは、EGFR-TKIが効かなくなり再発する原因を明らかにするため、EGFR変異陽性肺腺がん患者31名の検体から計39種類からなる肺がんオルガノイドを作成しました。この中には、EGFR-TKI治療後に再発したがん組織由来のオルガノイドが28種類含まれています。治療後再発した肺がん由来のオルガノイドは世界的にも限られており、今回樹立したオルガノイドはEGFR-TKIに対する再発原因を詳細に解析するための強力なツールになることが期待されます。
2)再発がん由来オルガノイドから「肺腺がん」と「肺扁平上皮がん」両方の特徴を持つ「ハイブリッドタイプ」を発見
樹立したオルガノイドの解析を行ったところ、再発後オルガノイドの約半数ですでに報告されている既知の再発原因を確認しました。しかし、残り半分の再発後オルガノイドでは再発の原因は不明でした。そこで、これら残り半分についてさらに詳細な検討を行ったところ、本来のタイプである「肺腺がん」と、別のタイプの「肺扁平上皮がん」の特徴を併せ持つ「ハイブリッドタイプ」に変化しているオルガノイドが複数存在することを見出しました。
今までの研究で、再発の原因として「肺腺がん」から「肺扁平上皮がん」への変化が起こることは報告されていましたが、「ハイブリッドタイプ」は研究チームが世界で初めて発見したものになります。
また、研究チームはこの「ハイブリッドタイプ」による再発が、現在最も使用されているEGFR-TKIであるオシメルチニブ(タグリッソ🄬🄬)の再発後の検体から作製した19種類のオルガノイドのうち5種類(26.3%)で起こっていることと、その5種類のオルガノイドでは、オシメルチニブに対する感受性が大きく低下していることを見出しました(下図)。
3)「ハイブリッドタイプ」再発がんに有効な薬剤の同定
研究チームは、これら「ハイブリッドタイプ」の再発がんに対して有効な薬剤の探索を行いました。その結果、CDK4/6阻害薬という種類の薬剤が「ハイブリッドタイプ」再発がんに有効である可能性を見出しました。そこで、マウスを使った動物モデルで「ハイブリッドタイプ」再発がんオルガノイドを移植し、マウス体内で腫瘍を形成させたのちにCDK4/6阻害薬の一つであるパルボシクリブを投与し、腫瘍形成スピードが低下するかを検証する実験を行いました。その結果、パルボシクリブによってマウス体内での腫瘍形成スピードも著しく低下することがわかりました(メイン画像)。これらのことから、「ハイブリッドタイプ」再発がんに対する治療薬としてCDK4/6阻害薬が有効であるという知見を得ました。
今後、「ハイブリッドタイプ」による再発を確認できた場合は、CDK4/6阻害薬による治療を行うことにより肺がんの進行を長期に抑えることが可能になり、患者の長期生存につなげられる可能性があります。
研究の社会的意義と展望:
・EGFR遺伝子変異陽性肺腺がんの治療成績向上
オルガノイドを用いた本研究成果をさらに深めて、EGFR-TKIの耐性化機序を明らかにし、治療後の再発に対しても有効な薬剤を探索・開発することで、EGFR遺伝子変異陽性肺腺がんの治療成績向上につながることが期待できます。とくに、CDK4/6阻害薬であるパルボシクリブ及びアベマシクリブは、現在乳がんで使用されている薬剤であり、肺がんへの適応拡大により、速やかに肺がん患者に提供できる可能性があります。
・肺がん以外のがんへの波及効果
現在、がん領域では多様な薬剤が開発され、治療初期の成績は急速に向上しています。一方、これら開発された薬剤の効果は多くの場合永遠ではなく、治療経過の途中で再発をきたします。「治療後の再発」の問題は近年のがん医療における大きな課題となっています。研究グループがおこなった、「治療後再発したがん検体からオルガノイドを樹立し再発原因を調べる」という研究手法は、肺がんのみでなく多くの他のがんに対しても適応できる手法です。本研究手法がさまざまながんで適応されることで、多くの種類のがんで再発の原因が解明されることが期待できます。
3.特記事項
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)次世代がん医療創生研究事業「がん多階層フェノタイプの理解に基づいた先端的創薬システムの開発」,革新的先端研究開発支援事業「新しい4次元モデルシステムを用いた腸管線維化疾患の病態解明」,次世代がん医療創生研究事業「肺癌オルガノイドライブラリー統合解析による癌の不均一性の解明と新規治療標的同定」,革新的がん医療実用化研究事業「肺癌オルガノイドライブラリーを用いた肺癌フェノタイプ多様性を規定する分子基盤解明と新規治療標的同定」、JSTMoonshotR&D「JPMJMS2022」、JSTERATO「JPMJER2303」、JSTFOREST「JPMJFR2215」、JSPS科研費JP21H02765,JP22K08290,JP21J12157、「日本学術振興会特別研究員」、「森正文肺癌制圧寄付研究講座」、「高橋産業経済研究財団」の支援によって行われました。
4.論文
タイトル:Basal-shift transformation leads to EGFR therapy-resistance in human lung adenocarcinoma
タイトル和訳: ヒト肺腺がんにおいて EGFR 治療抵抗性をもたらす新たな形質転換
著者:篠崎太郎、戸ヶ崎和博、浜本純子、光石彬史、福島貴大、杉原快、胡谷俊樹、岡田真彦、斎藤彩夏、茂松梨咲、高岡初誉、伊藤史麿、扇野圭子、石岡宏太、渡邊景明、比島恒和、紅林泰、江本桂、寺井秀樹、池村辰之介、川田一郎、朝倉啓介、菱田智之、浅村尚生、太田悠木、高橋シリラット、小田真由美、斎藤恵、股野麻未、副島研造、藤井正幸、福永興壱、安田浩之、佐藤俊朗
掲載誌:Nature Communications
DOI:10.1038/s41467-025-59623-3
【用語解説】
(注 1)オルガノイド:従来の細胞培養技術では多くの細胞はシート状に培養されています。オルガノイドは細胞増殖の足場となるジェルと増殖因子と呼ばれる細胞の増殖を促す分子を含む培養液により、立体的な細胞塊を形成するように育てられた培養細胞を指します。1つの幹細胞から生体内の組織に似た構造を培養皿の中で作り出すことが可能で、肺、胃、小腸、大腸、膵臓、肝臓など、さまざまな組織の正常細胞およびがん幹細胞を無限に増やすことが可能です。
(注 2)EGFR(上皮成長因子受容体):多くの細胞の表面には発現しているタンパクの一つ。このタンパクを作るもとになる遺伝子に異常(遺伝子変異)をきたすことで、肺がん(特に肺腺がん)が発症することが知られています。
(注 3)肺腺がん:肺がんにおけるもっとも多い組織型(顕微鏡で見た時の形態による分類)。
(注 4)肺扁平上皮がん:肺がんにおける組織型の一つ。腺がんの次に多いタイプです。
・詳細はこちら※参照元のサイトを開きます
https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2025/5/13/28-166945/
メイン画像:ハイブリッドタイプオルガノイドにパルボシクリブが有効である
下図:EGFRチロシンキナーゼ阻害剤を用いた1次治療がもたらす耐性の機序及びそれぞれに対する 2 次治療