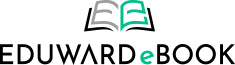寄稿者:北海道大学
《ニュース概要》
■ポイント
・好中球と好中球細胞外トラップについて基礎的事項を分かりやすく説明。
・好中球と糸球体構成細胞の相互作用についての最新知見を整理。
・腎疾患の病態形成における好中球と好中球細胞外トラップの役割について詳細に解説。
■概要
北海道大学大学院保健科学研究院の石津明洋教授、益田紗季子講師、西端友香講師、同大学大学院医学研究院の中沢大悟講師、楠(渡辺)加奈子助教、北海道大学病院の外丸詩野准教授らの研究グループは、腎疾患における好中球と好中球細胞外トラップの役割についての総説を発表しました。
好中球は末梢血白血球中の最多の免疫担当細胞で、従来は均質な細胞集団とみなされていましたが、近年、異なる遺伝子発現プロファイルと免疫特性を持つ多様な細胞群であることが分かってきました。感染などの刺激により活性化された好中球は、刺激の種類とそれを受け取るサブセットの違いに応じて、サイトカイン、ケモカイン、タンパク分解酵素、活性酸素、好中球細胞外トラップ(neutrophil extracellular traps:NETs)など様々な生理活性物質を放出します。このうち NETs は、脱凝縮した DNA と抗菌タンパクで構成されており、生体内に侵入した病原微生物を細胞外で捕捉・殺菌する重要な自然免疫機構の一つです。NETs は生体防御に不可欠である一方、その細胞毒性、血栓形成性、自己抗原性のために自己損傷のリスクも有しています。好中球と NETs は、急性腎障害、血管炎、全身性エリテマトーデス、血栓性微小血管障害、慢性腎臓病といった腎臓が障害される様々な病態の形成に関与しています。
本総説では、好中球の多様性について、NETs とは何か、好中球と糸球体構成細胞の相互作用について、腎疾患の病態形成における好中球と NETs の役割について、多くの文献を引用し詳述しています。これらを理解することは、好中球の活性化と NETs を標的とした腎疾患に対する新しい治療戦略の開発につながります。
なお、本総説は、2025 年 3 月 18 日(火)公開の Nature Reviews Nephrology 誌にオンライン掲載されました。
【背景】
好中球は末梢血白血球中の最多の免疫担当細胞で、従来は均質な細胞集団とみなされていましたが、近年、異なる遺伝子発現プロファイルと免疫特性を持つ多様な細胞群であることが分かってきました。感染などの刺激により活性化された好中球は、刺激の種類とそれを受け取るサブセットの違いに応じて、サイトカイン、ケモカイン、タンパク分解酵素、活性酸素、好中球細胞外トラップ(neutrophil extracellular traps:NETs)など様々な生理活性物質を放出します。
このうち NETs は、脱凝縮した DNA と抗菌タンパクで構成されており、生体内に侵入した病原微生物を細胞外で捕捉・殺菌する重要な自然免疫機構の一つです。NETs は生体防御に不可欠である一方、その細胞毒性、血栓形成性、自己抗原性のために自己損傷のリスクも有しています。
好中球の主要なサブセットである NDG*1 は、各種刺激に応じて、様々な形態の NETs を放出します(図 1)。その中には、NETs の主成分である DNA が核に由来するものやミトコンドリアに由来するもの、NETs 放出に伴い細胞死に至るものや至らないものがあり、これらの現象を引き起こす経路も多様です。NDG よりも未熟な好中球サブセットである LDG*2 は、NDG に比べて自然に NETs を放出しやすい性質があることも分かってきました。
【研究手法】
石津明洋教授らの研究グループは、好中球の多様性について、NETs とは何か、好中球と糸球体構成細胞の相互作用について、腎疾患の病態形成における好中球と NETs の役割について、分担して文献調査を実施し、これまでの知見を整理しました。
【研究成果】
本総説は、糸球体毛細血管壁の病理学的変化が腎内への好中球浸潤を促進し、浸潤した好中球は NETsを放出することで腎臓に存在する細胞、特にメサンギウム細胞や上皮細胞と相互作用し、組織損傷や炎症を拡大することを明確に示しました(図 2)。また、好中球と NETs は、急性腎障害、血管炎、全身性エリテマトーデス、血栓性微小血管障害、慢性腎臓病といった腎臓が障害される様々な病態の形成に関与していることを明示しました。
【今後への期待】
腎疾患の病態形成における好中球と NETs の役割を理解することは、好中球の活性化と NETs を標的とした腎疾患に対する新しい治療戦略の開発につながります。好中球の活性化を阻害する薬剤として、好中球細胞表面に発現する活性化受容体の拮抗薬や好中球に活性化シグナルを伝達する各種酵素の阻害剤、NETs の分解を促進する DNA 分解酵素などを用いた腎疾患に対する前臨床試験または臨床試験が国内外で展開されており、有効性が確認されることが期待されます。
【謝辞】
本研究は、厚生労働科学研究費 JPVAS(23FC1019)の助成を受けたものです。
■論文情報
・論文名
Neutrophils and NETs in kidney disease(腎疾患における好中球と好中球細胞外トラップ)
・著者名
中沢大悟 1、益田紗季子 2、西端友香 2、楠(渡辺)加奈子 1、外丸詩野 3、石津明洋 2(1 北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室、2 北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野、3 北海道大学病院病理部/病理診断科)
・雑誌名
Nature Reviews Nephrology(腎臓病学の専門誌)
・DOI
10.1038/s41581-025-00944-3
・URL
https://rdcu.be/ed4rq
・公表日
2025 年 3 月 18 日(火)(オンライン公開)
【用語解説】
*1 NDG
normal-density granulocyte の略語で、正比重顆粒球のこと。比重遠心法により多核白血球に分画される顆粒球。末梢血の主要な好中球サブセットである。
*2 LDG
low-density granulocyte の略語で、低比重顆粒球のこと。比重遠心法により単核白血球に分画される顆粒球。NDG よりも未熟な好中球と考えられている。
詳細はこちら※参照元のサイトを開きます
https://www.hokudai.ac.jp/news/2025/05/post-1864.html
メイン画像: 多様な好中球細胞外トラップ(NETs)
好中球の主要なサブセットである NDG は、各種刺激に応じて、様々な形態の NETs を放出する。その中には、NETs の主成分である DNA が核に由来するものやミトコンドリアに由来するもの、NETs 放出に伴い細胞死に至るものや至らないものがあり、これらの現象を引き起こす経路も多様である。
PMA(phorbol myristate acetate):ホルボールミリステートアセテート
LPS(lipopolysaccharide):リポ多糖
GM-CSF(granulocyte-monocyte colony-stimulating factor):顆粒球-単球コロニー刺激因子
C5a(complement 5a):補体 C5a
下図:好中球と糸球体構成細胞の相互作用
a. 糸球体毛細血管への好中球浸潤。内皮細胞には 70〜100 nm の孔があいているが、好中球は通常、サイズ制限と電荷障壁のために通過できない。しかし、糸球体毛細血管が障害される病的状態では、毛細血管壁のサイズ制限と電荷障壁が損なわれ、白血球尿が生じる。糸球体内皮細胞上の P-セレクチンと好中球細胞膜上の PSGL-1 などの相互作用が、好中球の血中から尿中への移動を媒介している。
b. メサンギウム細胞との相互作用。リポオキシゲナーゼにより産生されるロイコトリエン B4(LTB4)は好中球に、ロイコトリエン D4(LTD4)はメサンギウム細胞に作用して、これらの相互作用を促進する。さらに、好中球とメサンギウム細胞は Fcγ 受容体(FcγRs)や免疫複合体(ICs)を介しても相互作用する。
c. 上皮細胞との相互作用。糸球体毛細血管を越えた好中球は、上皮細胞と接触する。インターフェロン γ は上皮細胞上の ICAM-1 発現を誘導し、これは好中球細胞膜上のインテグリンと結合する。